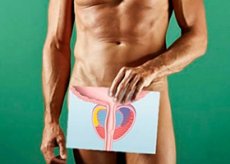
疫学
アメリカ国立衛生研究所によると、前立腺炎は男性の5~10%に影響を及ぼし、嚢胞(多くの場合、前立腺の炎症の結果として)は患者の10~20%で検出されます。
欧州泌尿器科学会によると、20~40歳の男性の約25%に、石灰化を伴う前立腺のびまん性変化が認められます。他のデータによると、石灰化は中年男性の約75%に認められ、良性前立腺肥大症(腺腫)患者の10%にも認められます。この疾患は、30~40歳では12人に1人、50~60歳では約4分の1、65~70歳以上では10人に3人が診断されます。腺腫は患者の40~50%で臨床的に重要な病状となります。
前立腺がんのリスクは、男性人口の14%に及んでいます。60%の症例では、65歳を超えた男性で腫瘍学的な診断が下されますが、40歳未満の男性で診断されることはほとんどありません。前立腺がんの診断時の平均年齢は約66歳です。
原因 前立腺のびまん性変化
泌尿器科医は、前立腺のびまん性変化の主な原因を、泌尿生殖器感染症(クラミジア、淋菌、ウレアプラズマ、トリコモナスなど)によって引き起こされる前立腺実質の長期炎症プロセスと関連付けています。
前立腺の腺組織、線維組織、または筋組織におけるびまん性変化の発症は、以下のことにも関連しています。
- 細胞内代謝の障害;
- 前立腺の血液循環の悪化およびその組織の栄養障害;
- 加齢に伴い前立腺が退縮し、前立腺硬化症が進行する過程で、腺組織が線維組織に置き換わること。
- 前立腺の悪性腫瘍および転移。
前立腺組織の変性に伴う石灰化は、石灰化(石灰化)領域の形成を伴い、超音波検査の結果、前立腺における石灰化を伴うびまん性変化として診断されます。また、分泌物の増加とその停滞によって形成された嚢胞を描出する場合、超音波診断医は前立腺におけるびまん性局所変化と診断します。
前立腺における形態学的びまん性変化には以下の種類があります。
- 萎縮 - 腺の細胞数と容積が限定的または広範囲に減少し、分泌機能と収縮機能が低下すること。
- 過形成 – 細胞の増殖により細胞の総数が増加すること。
- 異形成 – 細胞表現型の破壊を伴う異常な組織の変化。
萎縮過程はかなり長い期間にわたって進行し、前立腺に広範囲にわたる不均一な変化として現れることがあります。
良性前立腺肥大症または前立腺腺腫は、加齢に伴う疾患であり、間質細胞と上皮細胞の数が増加し、孤立した大きな結節が形成されます。結節は尿道付近に局在することが多く、超音波画像では前立腺のびまん性結節性変化として定義されます。詳細は「前立腺腺腫の原因と病態」をご覧ください。
最も悪性の変異は異形成と考えられており、前立腺の構造におけるこのような広範な変化は、細胞レベルでの変化の程度と段階に応じて、軽度、中等度、重度に分類されます。最初の2つのタイプは、通常、長期的な炎症プロセス、つまり慢性前立腺炎を示しています。これは組織の腫脹を伴い、膿瘍を引き起こす可能性がありますが、治療の影響で治癒することもあります。しかし、腫瘍専門医は、前立腺細胞の顕著な変化を、前立腺の基底細胞がんまたは腺がんの発生の前兆と見なしています。
危険因子
前立腺のびまん性変化のリスク要因には、炎症を引き起こす泌尿生殖器感染症、精巣損傷、アルコール乱用、寄生虫病、甲状腺および下垂体の病理、あらゆる局所の腫瘍に対する化学療法および放射線療法、特定の薬物(抗コリン薬、充血除去薬、カルシウムチャネル遮断薬、三環系抗うつ薬)の使用などがあります。
前立腺肥大症は、肥満、2 型糖尿病、高血中トリグリセリド値および低密度コレステロール値、動脈性高血圧などのメタボリック シンドロームと関連しているという証拠があります。
しかし専門家によると、主なリスク要因は加齢とそれに伴う精巣萎縮、そして精巣で産生される男性ホルモンであるテストステロンの減少です。加齢に伴うテストステロン産生の減少は40歳から始まり、年間約1~1.5%の割合で減少します。
 [ 15 ]
[ 15 ]
病因
前立腺炎における前立腺のびまん性変化の病因は、リンパ球、形質細胞、マクロファージ、および炎症性組織崩壊産物による前立腺組織への浸潤によって引き起こされます。炎症を起こした腺組織の一部が化膿して溶解すると、壊死塊で満たされた空洞が形成され、その後瘢痕化、すなわち正常組織が線維組織に置き換わります。
前立腺はアンドロゲンステロイドに依存する臓器です。加齢とともに、アロマターゼと5α-還元酵素の活性が高まり、これらの酵素の作用によりアンドロゲンはエストロゲンとジヒドロテストステロン(DHT、前駆物質のテストステロンよりも強力な)に変換されます。ホルモン代謝はテストステロンレベルの低下を招き、一方で前立腺細胞の成長に重要な役割を果たすDHTとエストロゲンの含有量を増加させます。
高齢男性の場合、前立腺実質のびまん性変化の病因は、単一または複数の線維性節の形成を伴う結合組織による腺組織の置換、ならびに前立腺腺房間質の病理学的増殖に関連しています。
前立腺のびまん性変化と石灰化は、組織の変性、不溶性線維性タンパク質(コラーゲン)および硫酸化グリコサミノグリカンの沈着によって生じます。石灰化は、前立腺実質への前立腺分泌物の沈着によっても形成されることがあります。石灰化は、非典型腺腫性過形成の3分の1の症例、および前立腺腺癌の52%の症例で観察されます。石灰化の後期段階は結石の形成であり、健康な男性では無症状の場合もあります。
嚢胞を伴う前立腺のびまん性局所変化は偶然発見され、泌尿器科医によると、その発生メカニズムは前立腺の萎縮、炎症、射精管の閉塞、腫瘍形成に関連しています。
症状 前立腺のびまん性変化
専門家によると、前立腺のびまん性変化の症状は、超音波検査で検出された疾患の症状としてのみ現れることを理解する必要があります。
ほとんどの場合、前立腺炎の初期症状は悪寒と頻尿で、超音波検査で前立腺の中等度の変化が確認できます。その後すぐに排尿時に灼熱感や刺すような痛みを伴う痛みが生じ、夜間にトイレに行かざるを得なくなり、痛みは鼠径部、腰部、陰部に広がり始めます。一般的な症状には、全身の倦怠感、疲労感の増加、関節痛、筋肉痛などがあります。
前立腺腺腫に伴う前立腺実質のびまん性変化により、まず排尿機能が低下します。腹筋が著しく緊張しているにもかかわらず、尿意切迫感(夜間を含む)が頻繁になり、排尿困難(膀胱筋への排尿圧の低下が影響)を呈し、排尿プロセス自体が期待されるほどの緩和効果をもたらさない状態です。同様に不快な症状として夜尿症が挙げられます。
医師によると、前立腺の石灰化を伴うびまん性変化は通常、症状を引き起こさず、多くの人がその存在に気づいていません。石は問題となり、炎症を繰り返す原因となると前立腺炎につながる可能性があります。患者が抗生物質を服用しても、腺管の閉塞は残るため、炎症プロセスが継続し、前立腺炎の症状が現れることがあります。
 [ 19 ]
[ 19 ]
診断 前立腺のびまん性変化
本質的には、前立腺のびまん性変化の診断は、経直腸超音波検査を使用して病理学的に変化した組織を特定することであり、これにより、この臓器の構造と大きさ、均一性/不均一性、密度、血管新生の程度を評価することができます。
前立腺疾患を正しく診断するには、脈動する超音波信号によって送られる超音波の反射度合いである音響密度(エコー輝度)の違いに基づいて前立腺組織の状態を視覚的に確認することが必要です。
前立腺の拡散的変化を示す特定のエコー徴候があります。
顕著な拡散変化がない場合、等エコー性として定義され、エコー画像では灰色で表示されます。
嚢胞性構造、特に嚢胞においては、超音波反射能の欠如、すなわち無エコー性(無エコー性)が内在しており、超音波画像ではこの部位に均一な黒点が出現します。膿瘍がある場合にも、超音波反射が弱い(低エコー性(暗灰色))場合にのみ、同様の「画像」が出現します。
ほとんどの場合、低エコーは前立腺の急性炎症などの炎症過程の証拠です。また、組織の浮腫、石灰化、または腺組織の線維組織への置換がある場合には、前立腺に低エコー領域を伴うびまん性不均一変化が観察されます。
しかし、超音波の反射が機器によって白い斑点の形で明瞭に記録される高エコー輝度は、結石や慢性前立腺炎を診断する根拠となります。
超音波診断基準は、診断を一義的に確定または否定するものではないことを覚えておく必要があります。超音波診断基準は、前立腺の構造的および機能的状態について医師に情報を提供するに過ぎません。正しい診断には、前立腺の直腸診(触診)、血液検査(一般検査、生化学検査、前立腺がん検査)、尿検査、精液検査などがあります。
さらに、排尿超音波、膀胱尿道鏡検査、尿流測定、ドップラー検査、前立腺のコンピューター断層撮影、MRI などの機器による診断も使用されます。
何を調べる必要がありますか?
どのように調べる?
どのようなテストが必要ですか?
差動診断
経直腸超音波検査の結果とすべての検査結果に基づいて鑑別診断が行われます。同一の臨床症状がある場合、同じ慢性型前立腺炎を腺癌、膀胱癌、またはパーキンソン病や多発性硬化症における神経性膀胱と区別する必要があるためです。
処理 前立腺のびまん性変化
もう一度繰り返しますが、治療されるのは前立腺の拡散した変化ではなく、超音波とその結果得られるエコー画像を使用して診断される疾患です。
つまり、前立腺炎、良性前立腺肥大症(腺腫)、前立腺硬化症、腺癌などの治療が処方されます。前立腺の炎症の治療に使用される薬は、出版物「慢性前立腺炎の治療」および資料「前立腺炎の錠剤」で詳細に説明されています。
良性前立腺肥大症の主な治療薬には、α遮断薬のタムスロシン(タムスリド、ハイパープロスト、オムスロシンなど)、ドキサゾシン(アルテシン、カミレン、ウロカード)、シロドシン(ウロレック)などがあります。また、5α還元酵素の活性を低下させる抗アンドロゲン薬のフィナステリド(プロステリド、ウロフィン、フィンプロス)、デュタステリド(アボダート)なども使用されます。
タムスロシンは、肝臓に問題がない場合、1日1回(朝、食後)1カプセル(0.4mg)を服用します。副作用には、脱力感、頭痛、心拍数の増加、耳鳴り、吐き気、腸障害などがあります。
フィナステリド(5mg錠)も1日1回1錠服用してください。副作用として、うつ状態、一時的な勃起不全、アレルギー性皮膚反応などが現れる場合があります。
医師は、サバル・セルラータヤシの果実の抽出物を含む薬剤ビタプロスト(錠剤および直腸坐剤)と薬剤パルプロステス(セルペンス、プロスタガット、プロスタモール)を推奨しています。
この植物はホメオパシーにも用いられています。多成分配合のジェントス(点滴剤と錠剤)に含まれており、1日3回、1錠(舌下投与)または15滴(内服)を2~3ヶ月間服用します。主な副作用は唾液分泌の増加です。
前立腺嚢胞が炎症を引き起こさない場合は、患者の状態をモニタリングし、ビタミン剤の投与を推奨します。しかし、嚢胞の大きさが排尿障害を引き起こすほど大きい場合は、嚢胞硬化療法が適応となります。
前立腺がんの治療方法については、前立腺がんの記事をご覧ください。
炎症または前立腺腺腫がある場合は、理学療法治療(UHF、直腸電気泳動、超音波および磁気療法、マッサージ)によって症状を改善できます。
外科的治療
前立腺疾患、特に前立腺腺腫においては、薬物療法が奏効しない場合に外科的治療が用いられることがあります。外科的治療には、腹腔鏡下経尿道的(尿道から)前立腺切除術と、膀胱からアクセスする開腹式腺腫摘出術があります。
低侵襲内視鏡法には、電波針焼灼術(経尿道的)、前立腺のレーザー塞栓術、電気またはレーザー蒸発法、マイクロ波熱凝固法などがあります。
民間療法
おそらく、前立腺の病変に対する最も有名な民間療法は、抗酸化作用のあるビタミン複合体、オメガ 6 脂肪酸、ホルモンの合成を刺激するリグナンを含むカボチャの種子の使用です。
効果的な自然療法としては、ウコン、緑茶、リコピンが豊富なトマトやスイカなどがあります。
良性前立腺肥大症に推奨される補完医療については、「前立腺腺腫の伝統的治療」をお読みください。
ハーブ療法は、イラクサの根、カモミールの花、トウキンセンカ、ノコギリソウ、ヤナギランの煎じ薬や煎じ液など、いくつかの症状の強さを軽減するのに役立ちます。


