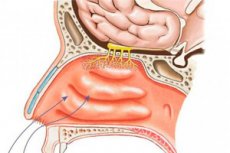
嗅覚機能の研究は、末梢神経系(PNS)および中枢神経系(CNS)の疾患を診断する上で非常に有効な方法として、極めて重要です。いわゆる本態性無嗅覚症または「パロスミア(嗅覚異常)」の多くは、嗅覚中枢およびその伝導体に直接的または間接的に関連する頭蓋内構造の特定の器質性疾患に関連している可能性があります。多くの場合、嗅覚障害(ほとんどの場合片側性)(例えば、客観的嗅覚低下または幻嗅)は、頭蓋内疾患の初期症状として現れることがあります。これらの状況において、最も有用な方法は、病態の動態と治療の有効性を判断することができる嗅覚機能の定量的評価です。
病歴
患者は、一般的に受け入れられている方法に従って問診を受けます。問診では、嗅覚の変化の兆候(低下、消失、知覚の亢進)や、匂いが連想や嗅覚異常を引き起こすかどうか(例えば、ある物質の匂いが別の物質の匂い、あるいはなじみのない物質の匂いとして知覚されるかどうか)を調べます。また、特定の匂いが気管支痙攣、動悸、あるいは自律神経反応を引き起こすかどうかも調べます。嗅覚障害の発生時期、周期性または持続性、動態、考えられる原因を明らかにします。さらに、嗅覚障害の直前および過去の疾患の性質、重症度、これらの疾患に伴う兆候(外傷、急性脳血管障害、感染症、中毒)、職業、職業上の危険(室内の刺激性および毒性のある液体の蒸気、エアロゾル、煙、粉塵)の有無も調べます。
嗅覚検査の方法は、主観的、間接的、客観的の3つに分けられます。日常の臨床診療では、被験者に試験物質を提示し、口頭で報告してもらう(「はい」「いいえ」「はい、でも判断できません」など、特定の匂いを告げる)主観的検査法が主に用いられます。
間接客観的方法は、皮質下嗅覚中枢の投射系、およびそれらの嗅幹構造と視床下部との関連における活性化に反応して生じる、いわゆる嗅覚栄養反応を客観的に記録することに基づいています。これらの反応には、心拍数の変化、呼吸周期の位相変化、呼吸数の変化、嗅球反射、皮膚電気反応の変化などが含まれます。これらの方法を用いる場合、嗅器官の機能の間接的な兆候は、「受容器 - 嗅球 - 皮質下嗅覚中枢」という反射経路によって実現される栄養反応の兆候です。ただし、これらの反応の存在は、嗅覚分析装置の正常な機能の絶対的な指標ではありません。3 番目の中性子の皮質領域で発生する孤立した障害は、分析装置の皮質機能 (知覚、認識、区別) に影響を及ぼしますが、損傷レベル以下 (3 番目の中性子の前) で発生する栄養反応の発生には影響しない可能性があるためです。
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]
客観的な方法は、ECoG および EEG の記録に基づいています。
ECoGは動物実験や脳神経外科手術において用いられ、生体電位を記録するための電極は大脳皮質の嗅覚野に配置されます。EEGでは、嗅覚分析装置の皮質領域の皮膚投射部(催眠馬の側頭基底部に位置する)に電極が配置されます。しかし、これらの研究結果には、ある程度の不信感を持って扱うべき側面もあります。ECoG電位が嗅覚刺激と同期し、その形状が典型的な振動と一致する場合にのみ、「受容器-皮質」反射経路が機能していると断言できます。しかし、この場合でも、知覚の質的側面に関する最終的な判断は未解決のままであり、例えばパロスミア現象がこれに該当します。嗅覚機能を評価するECoGおよびEEG法は、頭頂後頭側頭領域の容積測定過程を有する患者の包括的な検査において一定の価値があります。
嗅覚検査の方法は、定性的検査と定量的検査に分けられます。定性的検査では、まずPVを片方の鼻孔に、次にもう一方の鼻孔に近づけます。その間、患者は自ら嗅いで、匂いを感じるか、感じる場合はどのような匂いかを答えます。この検査を行うために、様々な著者が様々なPVのセットを提案しています。PVは、溶液の形で使用され、底栓付きの暗色の瓶に入れられます。瓶には番号が付けられ、対応するPVが指定されます。
例えば、N.S.ブラゴヴェシチェンスカヤ(1990)は、W.ボルンシュタイン(1929)の8つのPV(臭覚刺激物質)を、最も弱いもの(No.1)から最も強いもの(No.8)まで順に並べたセットについて報告している。洗濯用石鹸、ローズウォーター、ビターアーモンドウォーター、タール、テレピン(これらの物質は主に嗅神経に作用する)、アンモニア水、酢酸(嗅神経と三叉神経に作用する)、No.8 - クロロホルム(嗅神経と舌咽神経に作用する)である。嗅神経、三叉神経、舌咽神経にそれぞれ異なる作用を持つPVの使用には、一定の診断的価値がある。なぜなら、嗅神経が完全に遮断された状態でも、患者はV神経とIX神経に作用する「匂い」を依然として感じるが、その感覚は著しく弱まり、歪んだ形になるからである。
かつて、VI Voyachekの臭気測定セットが広く使用されていました。当初のバージョンでは、このセットは4種類の臭気強度の異なる臭気試験液(PV)で構成されていました。0.5%酢酸溶液(弱い臭気)、純エタノール(中程度の臭気)、バレリアンチンキ(強い臭気)、アンモニア水(超強臭気)です。後に、ガソリン(バレリアンの臭気に慣れていない技術者向け)と蒸留水(対照試験)がこのセットに追加されました。
ガソリンは、このセットの中で最も揮発性が高く、最も「浸透性」の高い物質であるため、VI Voyachek によって 6 番に分類されました。ガソリンが知覚されない場合、嗅覚は完全にオフになっているとみなされます。
定性的な嗅覚検査を正しく実施するには、実験をある程度標準化する必要があります。検査していない側の鼻に嗅覚蒸気が入り込む可能性を排除し、呼気時に逆行性の嗅覚蒸気がもう一方の鼻に入らないように、息を止めて吸入時に嗅覚評価を実施します。0.3×1 cmのろ紙を副木の隙間に固定し、嗅覚溶液で湿らせたものを片方の鼻孔に当て、もう片方の鼻孔を閉じます。被験者は鼻から軽く息を吸い込み、3~4秒間息を止めて、どのような匂いがするかを判断します。検査の結果は、被験者が感じる匂いに応じて5段階評価システムを用いて評価されます。
- 1 度 - 被験者は最も弱い匂い (1 番) を特定します。
- II 度 - 2、3、4、6 番目の匂いが知覚されます。
- III 度 - 3、4、6 番の匂いが知覚されます。
- IV度 - 匂い番号4、6が知覚されます。
- レベル V - 匂い番号 6 のみが認識されます。
匂いがまったく感じられない場合は、無嗅覚症と診断されます。
嗅覚低下の場合、その機械的な原因は除外されます。そのためには、鼻腔の上部を注意深く観察し、必要であれば、1:1000の塩化アドレナリン溶液(麻酔薬は使用しないでください)で粘膜を一度潤滑し、5分後に再度観察します。この処置後に嗅覚が出現または改善した場合は、「機械的な」嗅覚低下の存在を示します。
嗅覚機能の定量的研究には、知覚閾値と認識閾値の測定が含まれます。この目的のために、嗅覚刺激、三叉神経刺激、および混合作用刺激が用いられます。この方法の原理は、一定濃度の刺激を含む空気を投与するか、または知覚閾値に達するまで刺激濃度を徐々に増加させることです。
嗅覚を定量的に研究する方法はオルファクトメトリー(嗅覚測定法)と呼ばれ、この方法を実行する装置はオルファクトメーターと呼ばれます。このような装置の典型的な例としては、ツヴァールデメーカーとエルスバーグ・レーヴィのオルファクトメーターがあります。19世紀末、H. ツヴァールデメーカーはオルファクトメーターを設計しました。その動作原理は、サンプル採取管が、全体が高密度のPVで構成された円筒の中に設置され、外側は環境への昇華を防ぐためにガラスで覆われているというものです。サンプル採取管の先端が円筒の外側まで伸びると、PV蒸気は円筒内に入りません。
チューブがシリンダー内に引き込まれる際、シリンダー内に入るPVの量は、チューブからシリンダー端までの距離、すなわちチューブ内に流入できるPVの量に依存します。この方法の欠点は、被験者が制御不能な能動吸入をしてしまうことです。エルスバーグ-レヴィの「パルス」(インジェクター)法には、この欠点はありません。
エルスベルグ嗅覚計は、ポリビニルアルコール溶液が入ったフラスコで、ゴム栓で密閉されています。フラスコには、近位端にゴムホースが付いた2本のガラス管(短管と長管)が挿入されています。長管のホースは、蛇口またはクランプで閉じられます。短管のホースは、両端にオリーブが付いた2本の管に分岐しています。ノズル付きの注射器を使用して、長管からフラスコに空気が注入され、ポリビニルアルコールの蒸気が短管とオリーブを通して排出されます。ポリビニルアルコールのインジェクター供給の原理は、NS MelnikovaとLB Daynyak(1959)の嗅覚計に採用されています。その後、電気機械的および電子的にPVを投与し、温度、湿度、蒸気濃度によって匂い混合物を調整する複雑なシステムを備えた、より高度な様々な嗅覚計が開発されました。これらのシステムは、様々な供給モード(断続、連続、増加、減少)で使用されます。
嗅覚機能の定量的研究は、ろ紙と、たとえば0.2〜0.5%エチルアルコール溶液、0.2〜0.9%酢酸溶液などの範囲で、いずれかの物質の濃度を徐々に増加させることによって、非常に簡単な方法で行うことができます。このために、注射器を使用して、溶液からの嗅覚蒸気で飽和した空気の量を投与することが可能です(エルスバーグ-レヴィ法の改変)。この空気を注射器(10または20 ml)に吸い込み、次にこの空気を1、2、3 mlなどで鼻腔に導入して、匂いの感覚が現れます。後者の方法は簡単で信頼性が高く、材料費がほとんどかかりません。このような装置を構築するには、食酢溶液で1/3を満たしたフラスコ、クランプ付きのゴムホース2本が取り付けられた2本のガラス管が付いたゴム栓が必要です。ホースの1つにしっかりと挿入された注射器と、酢の蒸気が入ったフラスコから採取した空気を鼻に導入するための細いゴム製カテーテル。最終的な空気吸入の前に、注射器で2~3回吸引して、出口チューブを酢の蒸気で満たします。フラスコの空洞に挿入された吸入チューブのガラス端は、2番目のガラス管の端よりもかなり低く配置する必要がありますが、液体に触れないようにする必要があります。この方法の利点は、PVを鼻腔内の所望の深さ、嗅覚スリットまで強制的に導入できることです。これにより、PVの強制導入を提供しない方法で発生する制御不能な吸入の力が排除されます。
どのように調べる?


