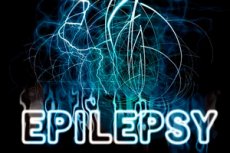
痙攣性疾患、てんかん、聖なる疾患、月の疾患など、恐ろしいほど予期せぬ周期的な発作を呈するこの疾患には様々な呼び名があります。発作の間、患者は突然床に倒れ込み、痙攣を起こして震えます。ここでは、現代医学では慢性進行性神経疾患とみなされるてんかんについてお話しします。てんかんの典型的な症状は、誘発性発作と非痙攣性発作の両方が、誘発されずに定期的に繰り返されることです。この疾患の結果、人格に異常が生じ、認知症や日常生活からの完全な離脱につながることがあります。古代ローマの医師クラウディウス・ガレノスでさえ、この疾患を2つのタイプに区別していました。特発性てんかんは遺伝性で、幼少期に症状が現れる原発性てんかんであり、二次性(症候性)てんかんは特定の要因の影響を受けて後年発症します。[ 1 ]
改訂版国際抗てんかん連盟(IALA)の分類では、てんかんの6つの病因カテゴリーの一つに遺伝性てんかんが挙げられています。遺伝性てんかんとは、遺伝的素因または新たに生じた遺伝子変異を伴う独立した原発性疾患です。本質的には、これは以前の版における特発性てんかんに相当します。この場合、患者は周期的にてんかん発作を繰り返す原因となり得る脳構造の器質的病変を有さず、発作間欠期に神経症状は認められません。既知のてんかんの病型の中で、特発性てんかんは最も予後が良好です。[ 2 ]、[ 3 ]、[ 4 ]
疫学
世界中で推定5,000万人がてんかんに罹患しており、そのほとんどは医療サービスを受けられていません。[ 5 ]、[ 6 ] 世界中の研究を対象としたシステマティックレビューとメタアナリシスによると、活動性てんかんの時点有病率は1,000人あたり6.38人、生涯有病率は1,000人あたり7.6人でした。てんかんの有病率は性別や年齢層による差はありませんでした。最も一般的な種類は、全般発作と原因不明のてんかんです。[ 7 ]、[ 8 ]
世界人口の平均0.4~1%が抗てんかん薬による治療を必要としています。先進国におけるてんかん発症率の統計では、年間10万人あたり30~50件のてんかん症候群の新規症例が記録されています。発展途上国では、この数値は2倍になると推定されています。てんかんの全形態のうち、特発性てんかんの症例は25~29%を占めています。[ 9 ]
原因 特発性てんかん
この疾患は、ほとんどの場合、小児および青年期に発症します。患者には、脳損傷を引き起こすような既往歴や外傷はありません。現代の神経画像診断法では、脳構造の形態学的変化の有無は判定できません。特発性てんかんの原因は、遺伝的に受け継がれた疾患発症素因(脳のてんかん原性)であり、直接的な遺伝によるものではないと考えられています。特発性てんかんの症例は、一般人口よりも患者の親族に多く見られるというだけです。[ 10 ]
家族性特発性てんかんの症例は稀で、現在5つのエピシンドロームにおいて単一遺伝子性常染色体優性遺伝が確認されています。遺伝子の変異により、良性家族性新生児および乳児てんかん、熱性発作を伴う全般てんかん、夜間発作を伴う焦点性前頭葉てんかん、聴覚障害を引き起こす遺伝子が特定されています。その他のエピシンドロームでは、病理学的過程の発症傾向が遺伝すると考えられます。例えば、脳のニューロン活動のあらゆる周波数範囲における同期は、てんかん性と呼ばれ、非興奮状態で脳膜の内側と外側に不安定な電位差が生じます。興奮状態において、てんかんニューロンの活動電位は基準値を大幅に超過し、てんかん発作の発症につながります。この発作が繰り返される結果、ニューロンの細胞膜は次第に損傷を受け、破壊されたニューロン膜を通して病的なイオン交換が形成されます。これにより悪循環が生じます。すなわち、過剰な神経放電の繰り返しによるてんかん発作は、脳組織の細胞に深刻な代謝障害をもたらし、それが次の発作の発症に寄与するのです。[ 11 ]
あらゆるてんかんに共通する特徴は、脳組織のまだ変化していない細胞に対するてんかんニューロンの攻撃性であり、これがてんかん性の拡散とてんかん過程の一般化に寄与します。
特発性てんかんでは、ほとんどの患者で全般発作がみられ、特定のてんかん焦点は認められません。現在、いくつかの種類の局所性特発性てんかんが知られています。[ 12 ]
若年性ミオクロニーてんかん(CAE)の研究では、染色体20q、8q24.3、1pが特定されています(CAEは後に若年性欠神てんかんと改名されました)。若年性ミオクロニーてんかんの研究では、染色体6p21.3のBRD2および染色体15q14のCx-36という感受性多型が、JMEの感受性増加と関連していることが示されています。[ 13 ],[ 14 ],[ 15 ] にもかかわらず、てんかんと診断された患者において、この遺伝子変異が認められることは依然としてまれです。
危険因子
特発性てんかんの発症リスク要因は仮説的なものであり、主なものは近親者てんかん患者の存在です。この場合、発症確率は2倍、あるいは4倍にまで高まります。特発性てんかんの病因は未だ完全に解明されていません。[ 16 ]
また、患者は脳を過興奮から保護する構造の弱さを遺伝的に受け継いでいる可能性も考えられます。これらの構造とは、橋、楔状核、または尾状核です。さらに、遺伝的素因を持つ人における疾患の発症は、脳のニューロンにおけるナトリウムイオンまたはアセチルコリンの濃度上昇につながる全身代謝病理によって引き起こされる可能性があります。ビタミンB群、特にビタミンB6の欠乏を背景に、全般性てんかん発作が発生することがあります。てんかん患者は、神経膠症(病理学的研究によると)の傾向があることが分かっています。神経膠症とは、死んだニューロンを置き換えるグリア細胞の過剰な拡散増殖です。興奮性の増加や、それを背景に痙攣性の準備状態を呈する他の要因も定期的に特定されています。
遺伝性てんかん(今後は遺伝性てんかんと呼ぶ)の発症リスク因子は、病態を誘発する遺伝子の変異です。さらに、遺伝子変異は必ずしも遺伝性である必要はなく、特定の患者において初めて発現することもあり、そのような症例は増加傾向にあると考えられています。
病因
特発性てんかんの発症機序は、遺伝的に規定された発作性反応、すなわち電気発生が障害されたニューロン群の存在に基づいています。外的要因による損傷や発作の誘発因子は検出されません。しかしながら、この疾患の発症年齢は様々であり、出生時から発症する患者もいれば、幼児期、思春期や青年期に発症する患者もいます。そのため、現段階では、病因の一部は明らかに未解明のままです。
症状 特発性てんかん
この疾患の主な診断徴候は、けいれん性および非けいれん性の両方のてんかん発作の存在です。これらの発作がなければ、特徴的な脳波、既往歴、患者の認知的・心理的特徴といった他のすべての症状は、「てんかん」の診断を確定するには不十分です。この疾患の症状は通常、最初の発作と関連しており、てんかんに関しては、これが最も正確な定義です。発作はより一般的な名称であり、原因を問わず、予期せぬ急激な健康状態の悪化を意味します。一方、発作は脳またはその一部の一時的な機能不全によって引き起こされる発作の特殊なケースです。
てんかん患者は、大発作や小発作、急性および慢性の精神障害(うつ病、離人症、幻覚、妄想)、持続的な人格変化(抑制、分離)など、さまざまな神経精神活動障害を経験することがあります。
しかし、繰り返しますが、てんかんの診断を可能にする最初の兆候は発作です。特発性てんかんの最も印象的な発作は、見逃すことのできない全般性発作、すなわち大発作です。ただし、以下に述べる症状群の全ての要素は、全般性発作であっても必ずしも当てはまるわけではないことをあらかじめ明記しておきます。特定の患者では、一部の症状しか現れない場合もあります。
さらに、通常、発作の前夜には前兆が現れます。患者の体調は悪化し始めます。例えば、心拍数の増加、頭痛、原因不明の不安感、怒りっぽさやイライラ、興奮や抑うつ、憂鬱感、無言などが現れます。発作前夜には、眠れずに一晩を過ごす患者もいます。通常、時間の経過とともに、患者は自分の状態から発作の兆候を察知できるようになります。
てんかん発作の形成は、前兆、強直間代発作、意識混濁の段階に分けられます。
オーラは発作の始まりを意味し、あらゆる種類の感覚の出現で現れることがあります - チクチクする感じ、痛み、温かいまたは冷たい感触、体のさまざまな部分へのそよ風(感覚的)、閃光、まぶしさ、稲妻、目の前の火(幻覚的)、発汗、悪寒、ほてり、めまい、口の渇き、片頭痛、咳、息切れなど(栄養的)。オーラは運動自動症で現れることがあります(運動)。患者はどこかに走り出し、体軸を中心に回転し始め、腕を振り回し、叫ぶ。時には片側の動き(左手、左足、体の半分)が行われます。精神的オーラは不安発作、現実感消失、幻覚、聴覚、感覚、視覚の幻覚よりも複雑な発作で現れることがあります。オーラがまったくないこともあります。
その後、すぐに第二段階、つまり発作そのものが始まります。患者は意識を失い、全身の筋肉が完全に弛緩(アトニー)し、倒れます。周囲の人にとっては予期せぬ転倒です(前兆は多くの場合、周囲の人々には気づかれません)。ほとんどの場合、患者は前方に倒れますが、後方や横に倒れるケースは比較的稀です。転倒後、強直性緊張期が始まります。全身または一部の筋肉が緊張し、硬直し、患者は伸び上がり、血圧が上昇し、心拍数が上昇し、唇が青くなります。筋緊張期は約30秒続き、その後、リズミカルな持続性収縮が始まります。強直期は間代性収縮に切り替わります。間代性収縮では、四肢(より急激な屈曲・伸展)、頭部、顔面筋、そして時には眼球(回旋、眼振)の断続的で無秩序な動きが増加します。顎のけいれんは、発作中に舌を噛む行動につながることがよくあります。これは、ほとんどすべての人に知られているてんかんの典型的な症状です。唾液分泌過多は口から泡を吹くことで現れ、舌を噛むと血が混じることが多い。喉頭筋の間代性けいれんにより、発作中にムー、うめき声などの音現象が発生する。発作中は、膀胱と肛門の括約筋が弛緩することが多く、不随意の排尿と排便につながる。間代性けいれんは1~2分続く。発作中、患者には皮膚反射と腱反射がない。発作の強直間代期は、徐々に筋肉が弛緩し、発作活動が弱まることで終了する。最初、患者は意識が混濁した状態にある。見当識障害、コミュニケーション困難(話しにくい、言葉を忘れる)などである。まだ震えがあり、一部の筋肉がけいれんしているが、徐々にすべて正常に戻る。発作後、患者は完全に疲れ果て、通常は数時間眠りに落ちる。目覚めると、無力症の症状(脱力感、倦怠感、機嫌の悪さ、視力障害)がまだ残っています。
特発性てんかんは、軽度の発作を伴う場合もあります。これらには、単純性欠神発作と定型性欠神発作が含まれます。複雑性非定型欠神発作は、特発性てんかんの特徴ではありません。典型的な発作は、患者が凝視したまま固まる、全般性短期発作です。欠神の持続時間は通常1分以内で、その間に患者の意識は途切れますが、転倒はしませんが、手に持っていたものをすべて落とします。患者は発作のことを覚えておらず、中断された活動を続けていることがよくあります。単純性欠神は、前兆や発作後の意識混濁を伴わずに発生し、通常はまぶたや口を中心とした顔面筋の痙攣、および/または口腔自動症(唇を鳴らす、噛む、舐める)を伴います。時には、患者が気づかないほど短期間の非痙攣性欠神発作もあります。患者は、突然視界が暗くなったと訴えます。この場合、彼の手から落ちた物体がてんかん発作の唯一の証拠である可能性があります。
推進性発作(うなずき、つつき、「サラーム発作」など、頭部または全身を前方に動かす動き)は、姿勢保持筋の筋緊張低下によって引き起こされます。患者は転倒しません。主に4歳未満の乳幼児に見られ、特に男児に多く見られます。これはこの病気の夜間発作の特徴です。年齢を重ねると、これらの発作は重度のてんかん発作に置き換わります。
ミオクローヌスは、筋肉の急速な反射収縮であり、ピクピクとした動きとして現れます。痙攣は全身に現れる場合もあれば、特定の筋肉群にのみ現れる場合もあります。ミオクローヌス発作時に記録された脳波では、てんかん性放電の存在が認められます。
強直性 – 体の筋肉群または筋肉全体の持続的な収縮。その間、特定の姿勢が長時間維持されます。
脱力性 - 筋緊張の断片的または完全な消失。転倒や意識喪失を伴う全身性脱力は、てんかん発作の唯一の症状である場合もあります。
発作は混合性であることが多く、欠神発作と全般性強直間代発作、ミオクロニー発作と脱力発作などが組み合わされます。非けいれん性の発作が発生することもあり、幻覚やせん妄を伴う薄明意識、さまざまな自動症やトランス状態などが起こります。
フォーム
特発性てんかんに関連する症例の大部分は、小児期および思春期に発症します。このグループには、比較的良性のてんかん症候群が含まれます。つまり、治療によく反応するか、治療を全く必要とせず、てんかん発作以外の神経学的状態に影響を与えることなく経過します。また、知的発達の面でも、子どもたちは健常者と比べて遅れをとることはありません。脳波では基本的なリズムが保たれており、現代の神経画像診断法では脳の構造的異常は検出されませんが、これは実際に異常が存在しないことを意味するものではありません。時には、後になって異常が発見されることがあり、その異常が「見落とされた」のか、それとも発作を引き起こしたのかは、まだ明らかではありません。
特発性てんかんは発症年齢が異なり、一般的に予後は良好です。しかし、ある病型が別の病型に変化する場合もあります。例えば、小児期の欠神てんかんが若年性ミオクロニーてんかんに変化するケースなどです。近親者が小児期および成人期に特発性てんかんを発症した場合、このような病型変化や後年の発作発生の可能性が高まります。
特発性てんかんの種類は明確に定義されておらず、分類基準に矛盾があり、小児欠神てんかんなど一部の形態には厳密な診断基準がありません。
特発性全般てんかん
この疾患の最も初期の形態である良性の家族性および非家族性の新生児/乳児てんかんは、満期産児において生後2日目または3日目に検出されます。また、これらの子どもは主に、重大な合併症なく妊娠・出産を無事に終えた女性から生まれます。家族性てんかんの平均発症年齢は6.5ヶ月、非家族性てんかんは9ヶ月です。現在、家族性てんかんの発症に関連する遺伝子(8番染色体長腕および20番染色体長腕)が特定されており、その変異が家族歴にてんかん発作の症例があったという事実以外に、他の誘発因子は見当たりません。この形態の乳児では、非常に頻繁(1日最大30回)に、1~2分間の短い発作が観察されます。発作は、全身発作、焦点発作、または局所性強直間代発作を伴い、無呼吸発作を伴います。[ 17 ]
小児特発性ミオクローヌスてんかんは、ほとんどの患者に発症し、生後4ヶ月から3歳の間に発症します。本疾患は、意識が保たれたミオクローヌスのみを特徴とし、一連の衝動的な動き(眼球の外転を伴う頭部の素早いうなずき運動)が見られます。場合によっては、けいれんが肩甲帯の筋肉にまで広がることがあります。歩行中に衝動性発作が始まると、落雷に見舞われます。発作の誘発は、鋭い音、予期せぬ不快な接触、睡眠の中断または覚醒によって引き起こされる場合があり、まれに、リズミカルな光刺激(テレビの視聴、電気の点灯/消灯)によっても引き起こされることがあります。
ミオクロニー・アトニー発作を伴う小児てんかんは、特発性(遺伝性)全般性疾患の一種です。発症年齢は10ヶ月から5歳です。ほとんどの患者は、30~120秒間続く全般発作を直ちに発症します。特徴的な症状として、四肢のミオクローヌス(体幹の推進的なうなずき運動)に起因する、いわゆる「膝蹴り」が挙げられます。発作中は通常、意識は保たれます。アトニー要素を伴うミオクローヌスは、しばしば定型的欠神発作を伴うことが多く、この間意識は消失します。欠神発作は朝の起床後に観察され、高頻度で発生し、ミオクローヌス要素が加わることもあります。さらに、全般性ミオクロニー・アトニーてんかんの小児の約3分の1は部分運動発作も併発します。この場合、特に発作が頻繁に観察される場合、予後は悪化します。これはレノックス・ガストー症候群の発症の兆候である可能性があります。
小児全般特発性てんかんには欠神型のてんかんも含まれます。
乳児欠神てんかんは生後4年間に発症し、男児に多く見られます。主に単純欠神発作として現れます。約2/5症例では、欠神発作にミオクロニー発作や失調発作が併存します。2/3症例では、全般性強直間代発作として発症します。小児では発達に遅れが生じる場合があります。
小児欠神てんかん(ピクノレプシー)は、5歳から7歳の小児に最も多く発症し、特に女児に多く見られます。ピクノレプシーは、2秒から30秒の間、突然の意識消失または著しい混乱と、非常に頻繁な発作(1日に約100回)を特徴とします。発作時の運動症状は最小限か全くみられませんが、典型的な欠神発作の前に前兆があり、発作後に意識混濁が見られる場合は、偽欠神発作に分類されます。
ピクノレプシーは、ミオクローヌス、強直性けいれん、無緊張状態など、様々な要素を伴う非定型欠神発作を引き起こすことがあります。また、自動症が観察されることもあります。様々な出来事が発作頻度の増加を刺激する可能性があり、例えば突然の覚醒、激しい呼吸、急激な照明の変化などが挙げられます。患者の3分の1では、発症後2年目または3年目に全般性けいれん発作が加わることがあります。
若年性欠神てんかんは思春期および青年期(9歳から21歳)に発症し、約半数の症例では欠神発作から始まり、全般性けいれん発作で始まることもあります。全般性けいれん発作は、睡眠中断、覚醒、または就寝時によく起こります。発作頻度は2~3日に1回です。欠神発作の発症を刺激する因子は過換気です。欠神発作には、顔面筋の痙攣、または咽頭および口腔の自動症が伴います。患者の15%では、近親者にも若年性欠神てんかんの病歴があります。
ミオクローヌス欠神発作(タッシナーリ症候群)は、別個に区別されます。発症年齢は1歳から7歳で、特に午前中に頻繁な欠神発作と、肩甲帯および上肢の強い筋収縮(ミオクローヌス)を特徴とします。この病型では光過敏症は典型的ではなく、発作の誘発因子は過換気です。罹患児の半数では、多動性行動や知能低下を背景に神経障害が認められます。
成人における特発性全般てんかんは、成人期てんかん症例全体の約10%を占めます。専門家は、20歳、さらには30歳以上の患者にこのような診断所見が見られるのは、患者本人やその家族が小児期の欠神発作やミオクロニー発作を放置し、長期間(5年以上)かけて再発したために診断が遅れたためだと考えています。また、この疾患が極めてまれに、非常に遅い段階で発症することもあると考えられています。
また、病気が後期に発症する原因としては、誤診とそれに伴う不適切な治療、発作に対する適切な治療への抵抗、治療中止後の特発性てんかんの再発などが挙げられます。
特発性局所てんかん
この場合、この疾患の主な、そしてしばしば唯一の症状は、部分発作(局所性、焦点性)です。この疾患のいくつかの形態では、それぞれの発作に関連する遺伝子がマッピングされています。これらの発作には、特発性後頭葉てんかん、感情発作を伴う部分発作、家族性側頭葉てんかん、そして本態性読字てんかんがあります。
その他の症例では、局所性特発性てんかんは遺伝子変異の結果として発症することが分かっているものの、原因となる遺伝子は正確には特定されていません。これらの症例には、常染色体優性夜間前頭葉てんかんと聴覚症状を伴う焦点性てんかんがあります。
最も一般的な局所性疾患はローランドてんかんです(15歳未満で発症するてんかん症例全体の15%を占めます)。この疾患は3歳から14歳の小児に発症し、5歳から8歳がピークです。特徴的な診断徴候は、いわゆる「ローランドピーク」、つまり発作間欠期に記録される脳波上の複合症状です。これらは小児良性てんかん発作とも呼ばれます。このタイプのてんかんにおけるてんかん焦点は、脳のローランド周囲領域およびその下部に局在します。ローランドてんかんは、ほとんどの場合、正常な神経学的状態(特発性)の小児に発症しますが、中枢神経系の器質性病変が検出される場合は、症候性の症例となることもあります。
患者の大多数(最大 80 %)では、この疾患は主に、睡眠中に始まるまれな(月に 2 回または 3 回)単純焦点発作として発現します。患者は、目覚めたとき、または日中の発作中に、体性感覚前兆(口腔(舌、歯茎)または咽頭を含む片側性の感覚異常)で始まることに気付きます。その後、焦点発作が発生します。顔面筋のけいれん性収縮は症例の 37 %で発生し、口と咽頭の筋肉のけいれん性収縮は 53 %で発生し、重度の唾液分泌過多を伴います。睡眠中、患者はゴロゴロ、ゴロゴロという音を発します。患者の 5 分の 1 では、肩と腕の筋肉が筋肉の収縮に関与しており(腕筋膜発作)、2 倍の頻度で下肢(片側性)に広がることがあります。時間の経過とともに、筋肉の収縮の局在が変化する可能性があり、体の反対側に移動します。約4分の1の症例では、睡眠中に二次性全般発作が発生することがありますが、これは特に低年齢の小児に多く見られます。15歳までは、97%の患者が治療により完全に寛解します。
はるかにまれなのが、晩発性特発性後頭葉てんかん(ガストー型)です。これは別の病気で、3歳から15歳に発症し、8歳でピークを迎えます。非けいれん性発作が頻繁に起こり、急速に発現して数秒から3分間続く基本的な幻覚として表現され、日中または起床後に多く見られます。平均して、発作頻度は週1回です。圧倒的多数の症例では、患者は発作状態で接触しません。発作は、まばたき、痛みの錯覚、失明などの症状の出現とともに進行する可能性があります。嘔吐はまれです。頭痛を伴う場合があります。複雑な幻覚、その他の症状、二次的な全般発作を発症する人もいます。15歳までに、ガストー症候群と診断された患者の82%が治療による寛解に達します。
パナイオトプロス症候群も、以前の形態の変異体として区別されます。これは、古典的なガストー症候群の10倍の頻度で発生します。このタイプの特発性後頭葉てんかんは、早期に発症することがあります。症状のピークは3〜6歳ですが、この症候群は1歳児や8歳児にも発症する可能性があります。さらに、発作を繰り返すリスクが最も高いのは、早期発症に関連しています。発作は主に栄養症状を呈し、主な症状は嘔吐であるため、診断されていない症例もあると考えられています。子供の意識は損なわれていませんが、体調不良と激しい吐き気を訴えますが、激しい嘔吐とともに解消し、意識混濁や痙攣などの他の症状が現れます。パナイオトプロス症候群の発作の別の形態は、失神または失神です。失神は強直性またはミオクローヌス性の要素を伴い、尿失禁や便失禁を伴うこともあります。最終的には無力症と睡眠状態に陥ります。発作は30分から7時間と長く、通常は夜間に始まります。発作の頻度は低く、発症期間中に1回しか発作が起こらない場合もあります。パナヨプロス症候群の患者の92%において、最大9年間の寛解が認められます。
情動発作を伴う良性小児てんかん(ダル・ベルナディン症候群)も、後頭葉てんかんまたはローランドてんかんの一種と考えられています。発症は2歳から9歳の間に記録されています。発作は、恐怖発作、泣き声、叫び声に似ており、顔面蒼白、発汗増加、流涎、腹痛、自動症、錯乱などの症状が見られます。発作は睡眠中、つまり入眠直後に発症することが多いですが、日中に起こることもあります。また、会話中や目に見える刺激のない活動中にも、自発的に発作を起こします。ほとんどの場合、18歳になる前に寛解します。
上記の部分性特発性てんかんは小児期にのみ発症します。その他のてんかんはいつでも発症する可能性があります。
光過敏性局所性特発性てんかんは、後頭部に症状が現れる疾患です。発作は自発発作と同一ですが、栄養症状が加わる場合があり、二次性全般性強直間代発作へと発展することもあります。発作の誘発因子は頻繁な閃光であり、特にビデオゲームやテレビ視聴中に発作が起こることが多いです。発症年齢は15ヶ月から19歳です。
聴覚症状を伴う特発性部分てんかん(側頭葉、家族性)は、聴覚現象を伴う前兆の出現から始まります。患者は、打撃音、カサカサという音、シューという音、キーンという音、その他の耳障りな音、複雑な幻聴(音楽、歌声)を聞き取ります。これらの音を背景に、二次性全般化発作が生じることもあります。発症年齢は3歳から51歳です。この病型の特徴は、発作頻度が低く、予後が良好であることです。
偽全般発作を伴う特発性部分てんかんは、非定型欠神発作、脱力発作、眼瞼ミオクローヌスに部分運動発作が組み合わさったもので、脳波ではてんかん性脳症に類似することがあります。しかし、小児では神経学的欠損はなく、神経画像検査では構造的欠陥は認められません。
夜間発作を伴う遺伝的に決定される家族性常染色体優性前頭葉てんかんもあります。発症時期の幅は非常に広く、発作は2歳から56歳まで発症する可能性があります。正確な有病率は不明ですが、世界中で家族の数は増加しています。過運動発作はほぼ毎晩発生します。持続時間は30分から50分です。間代性けいれんが加わることが多く、患者は我に返ると床に横たわっていたり、通常とは異なる体勢や場所にいたりします。発作時には鋭い覚醒があり、意識は保たれ、発作後に患者は再び眠りに落ちます。発作の発症は、常に睡眠、つまり睡眠前、睡眠中、または睡眠後に起こります。発作は通常は生涯続き、高齢になると頻度は少なくなります。
読書てんかん(筆記性、言語誘発性)は、まれな特発性てんかんの一種です。発症は思春期後期(12~19歳)に起こり、10代の男子に多く見られます。発作は、読書、書字、または会話の開始直後に始まります。誘発刺激は言語であり、書面だけでなく口頭でも構いません。口と喉頭の筋肉が関与する短いミオクローヌスが発生します。患者が読書を続けると、発作はしばしば全般性強直間代発作へと発展します。まれに、幻視が加わる場合があります。言語障害を伴う長時間の発作が起こることもあります。患者の行動が適切に構造化されていれば、重度の発作は発生しません。予後は良好な形態です。
合併症とその結果
特発性加齢依存性てんかんは一般的に治療可能であり、場合によっては治療を全く必要とせず、後遺症もなく経過することもあります。しかし、症状を無視して自然に治まることを期待するのは得策ではありません。特に脳が成熟し人格が形成される幼少期や青年期におけるてんかん様活動は、神経学的欠損の発現の一因となり、認知能力の低下や将来の社会適応の困難につながります。さらに、一部の患者では発作が形質転換し、成人期に入ってから発症することもあり、生活の質を著しく低下させます。このような症例は、遺伝的素因と治療の早期中止、あるいは治療の実施の欠如の両方に関連しています。
さらに、てんかん性脳症は小児期にも発症する可能性があり、その症状は初期段階では良性特発性脳症に類似することが多いため、患者の徹底的な検査とそれに続く治療が緊急に必要です。
診断 特発性てんかん
この疾患の診断基準は、てんかん発作の存在です。この場合、患者は包括的に検査を受ける必要があります。患者本人だけでなく家族の病歴を徹底的に収集するとともに、臨床検査とハードウェア検査を実施します。現在、臨床検査によるてんかんの診断を確定することは不可能ですが、患者の全般的な健康状態を明らかにするために臨床検査は必須です。
発作の原因を特定するために、機器による診断も行われます。主な機器検査法は、発作間欠期、そして可能であれば発作中の脳波検査です。脳波の解析は、ILAE(国際てんかん連盟)の基準に従って行われます。
ビデオモニタリングも使用され、その発生を予測したり刺激したりすることが非常に難しい短い発作を観察することが可能になります。
特発性てんかんは、脳構造に器質的損傷がない場合に診断されます。診断には、コンピューター画像検査や磁気共鳴画像法といった最新の神経画像診断法が用いられます。心電図検査と心エコー検査は、心機能を評価するために処方され、多くの場合、動態および負荷時の心機能を評価するために行われます。血圧は定期的にモニタリングされます。[ 18 ]
患者には神経心理学的検査、耳神経学的検査、神経眼科学的検査も処方されます。その他の検査も必要に応じて処方されることがあります。
差動診断
特発性てんかんの鑑別診断は非常に複雑です。第一に、この症例では脳組織における構造変化は検出されません。第二に、発症年齢によっては患者への問診が困難な場合が多く、第三に、てんかん発作は、失神、心因性発作、睡眠障害、その他神経疾患や身体疾患に起因する症状に紛れてしまうことがよくあります。
てんかん発作は、栄養発作や心因性発作、ミオジストニア、発作性筋麻痺、失神、急性脳血管障害におけるてんかん様発作、睡眠障害など、様々な病態と鑑別されます。立ち姿勢、過食、熱いお風呂、息苦しさといった発作誘発因子の存在、顕著な感情的要素、特徴的でない臨床像と持続時間、発作後の意識混濁や睡眠といった症状の欠如、てんかんを患っている近親者がいないこと、その他の矛盾点などには注意が必要です。この疾患の重篤性と抗てんかん薬の毒性を考慮すると、回復の予後だけでなく患者の生命も、正しい診断にかかっている場合が多いのです。[ 19 ]
連絡先
処理 特発性てんかん
基本的に、様々な形態の特発性てんかんは、長期寛解と再発の回避を達成するために、特に若年性欠神てんかんやミオクロニーてんかんの場合、長期にわたる薬物療法を必要とします。場合によっては、生涯にわたる薬物療法が必要となることもあります。例えば、良性の家族性新生児てんかんはほとんどの場合自然に治まるため、抗てんかん療法が必ずしも正当化されるとは限りませんが、それでも短期間の薬物療法が処方されることがあります。いずれにせよ、その適切性、薬剤の選択、治療期間は、患者を徹底的に診察した上で、医師が個別に決定する必要があります。
特発性全般てんかん(点頭てんかんを含む様々な形態)および局所発作において、バルプロ酸が最も効果的であることが証明されています。バルプロ酸単独療法では、75%の症例で治療効果が得られます。他の抗てんかん薬との併用も可能です。[ 20 ]
デパキンやコンブレックスなどの有効成分バルプロ酸ナトリウム(バルプロ酸)を含む薬剤は、典型的な欠神発作、ミオクロニー発作、強直間代発作、脱力発作の発生を予防します。これらの薬剤は光刺激を除去し、てんかん患者の行動および認知の逸脱を修正します。バルプロ酸の抗てんかん作用は、おそらく2つの経路で発揮されます。用量依存的な主な作用機序は、血中、ひいては脳組織中の有効成分濃度の直接的な上昇であり、γ-アミノ酪酸含有量の増加に寄与し、抑制プロセスを活性化します。2つ目の作用機序は、仮説的には、脳組織におけるバルプロ酸ナトリウム代謝物の蓄積、または神経伝達物質の変化に関連している可能性があります。この薬剤がニューロンの膜に直接作用する可能性があります。バルプロ酸誘導体に過敏症のある方、家族歴のある慢性肝炎の患者、および本剤の補助成分の分解に関与する酵素の欠損を伴う肝性ポルフィリン症の患者には禁忌です。また、幅広い副作用の発現は用量依存的です。造血、中枢神経系、消化器および排泄器官、免疫系に副作用が生じる可能性があります。バルプロ酸には催奇形性があります。ラモトリギンとの併用療法は、ライエル症候群に至るアレルギー性皮膚炎の発症リスクが高いため推奨されません。バルプロ酸とセントジョーンズワートを含むハーブ製剤の併用は禁忌です。これらの薬剤は神経精神薬と慎重に併用し、必要に応じて用量を調整する必要があります。[ 21 ]
γ-アミノ酪酸の抑制効果を高めるクロナゼパムは、あらゆるタイプの全般発作に効果的な治療薬です。短期間の治療で、治療効果のある低用量で使用されます。特発性てんかんでは、長期間の投与は望ましくありません。副作用(発作やけいれんの増加といった逆説的な副作用を含む)や、比較的急速な依存性の発現により、本剤の使用は制限されます。睡眠中の呼吸停止、筋力低下、意識混濁を起こしやすい患者には禁忌です。また、過敏症の患者や重度の肝不全/腎不全の患者にも処方されません。催奇形性があります。
ラモトリギンは、全般性欠神発作および強直間代発作の抑制に役立ちます。ミオクロニー発作の抑制には、その作用が予測不可能なため、通常は処方されません。本剤の主な抗てんかん作用は、ニューロンのシナプス前膜のチャネルを通るナトリウムイオンの流れを遮断する作用と関連しており、これにより、てんかん発作の発症において最も一般的かつ重要な興奮性神経伝達物質、特にグルタミン酸の過剰な放出を抑制します。その他の作用としては、カルシウムチャネル、GABA、およびセロトニン作動性メカニズムへの影響が挙げられます。
ラモトリギンは、従来の抗てんかん薬に比べて副作用が少なく、必要に応じて妊娠中の患者にも使用できます。全般性てんかんおよび局所性特発性てんかんの第一選択薬と言われています。
エトスクシミドは単純欠神発作(小児欠神てんかん)の第一選択薬です。しかし、ミオクローヌスに対する効果は低く、全般性強直間代発作に対する抑制効果は事実上ありません。そのため、全般性強直間代発作の発現リスクが高い若年性欠神てんかんには、現在では処方されていません。最も一般的な副作用は、消化不良症状、発疹、頭痛などですが、血液検査値の変化や四肢の振戦がみられる場合もあります。まれに、逆説的な副作用、すなわち重度のてんかん発作が現れる場合があります。
フルクトース誘導体である新しい抗てんかん薬トピラマートも、特発性てんかんの全般発作および局所発作の抑制に推奨されています。ラモトリギンや従来の抗てんかん薬とは異なり、感情症状を緩和することはできません。この薬はまだ研究段階ですが、てんかん発作の抑制効果はすでに実証されています。その作用機序は、電位依存性ナトリウムチャネルの遮断に基づいており、反復興奮電位の発生を抑制します。また、抑制性メディエーターであるγ-アミノ酪酸の活性化を促進します。トピラマート服用時の依存性に関する情報はまだありません。6歳未満の子供、妊娠中および授乳中の女性、および薬剤の成分に過敏症のある人には禁忌です。トピラマートは、中枢性抗てんかん作用を持つ他の薬剤と同様に、多くの副作用があります。
特発性てんかんの治療に使用されるもう一つの新薬はレベチラセタムです。その作用機序は十分に解明されていませんが、ナトリウムチャネルおよびT-カルシウムチャネルを遮断せず、GABA作動性伝達を増強しません。抗てんかん作用は、薬物がシナプス小胞タンパク質SV2Aに結合することで発現すると考えられています。レベチラセタムは、中等度の抗不安作用および抗躁作用も示します。
現在進行中の臨床試験において、この薬剤は部分発作の抑制に有効な手段であり、また全般性ミオクロニー発作および強直間代発作の複合療法における追加薬剤としても有効であることが証明されています。しかしながら、レベチラセタムの抗てんかん作用に関する研究は継続されます。
現在、欠神発作を伴う特発性全般てんかんの治療薬として選択される第一選択薬は、バルプロ酸、エトスクシミド、ラモトリギン、またはバルプロ酸とエトスクシミドの併用による単剤療法です。単剤療法の第二選択薬は、トピラマート、クロナゼパム、レベチラセタムです。治療抵抗性の症例では、多剤併用療法が用いられます。[ 22 ]
ミオクロニー発作を伴う特発性全般てんかんは、次のように治療することが推奨されています。第一選択薬 – バルプロ酸またはレベチラセタム、第二選択薬 – トピラマートまたはクロナゼパム、第三選択薬 – ピラセタムまたは多剤療法。
全般性強直間代発作は、バルプロ酸、トピラマート、ラモトリギンの単独療法で治療され、第二選択薬はバルビツール酸、クロナゼパム、カルバマゼピンで、多剤療法で治療されます。
全般性特発性てんかんの場合、てんかん重積状態に至るまで発作頻度を増加させる可能性があるカルバマゼピン、ハパベンチン、フェニトインなどの古典的な抗てんかん薬の処方は避けることが望ましいです。
局所発作は、依然としてカルバマゼピン、フェニトイン、またはバルプロ酸を有効成分とする古典的な薬剤によるコントロールが推奨されています。ローランドてんかんの場合は単剤療法が用いられ、抗てんかん薬(バルプロ酸、カルバマゼピン、ジフェニン)は最小有効用量で処方されます。複合療法やバルビツール酸は使用されません。
特発性部分てんかんでは、通常、知的障害や記憶障害は認められないため、専門医は積極的な抗てんかん薬の多剤併用療法は必要ではないと考えています。そこで、古典的な抗てんかん薬による単剤療法が用いられます。
治療期間、投与頻度、投与量は個別に決定されます。薬物治療は、発作が再発した場合にのみ処方することが推奨され、最後の発作から2年が経過すれば、薬物の中止を検討できます。
発作の病因には、ビタミンB群、特にビタミンB1、B6、セレン、マグネシウムの欠乏がしばしば見られます。抗てんかん療法を受けている患者では、ビオチン(B7)やビタミンEなどのビタミンやミネラル成分の含有量も減少します。バルプロ酸を服用している場合、レボカルニチンは発作活動を抑制します。ビタミンD欠乏症が生じ、カルシウム吸収不良や骨粗鬆症を引き起こす可能性があります。新生児では、葉酸欠乏症によって発作が起こることがあります。母親が抗てんかん薬を服用していた場合、ビタミンK欠乏症が生じ、血液凝固に影響を与える可能性があります。特発性てんかんにはビタミンやミネラルが必要な場合がありますが、その使用の妥当性は医師の判断に委ねられています。無秩序な使用は望ましくない結果をもたらし、病気の経過を悪化させる可能性があります。[ 23 ]
理学療法は、発作中のてんかんには用いられません。理学療法、運動療法、マッサージは、寛解開始から6ヶ月経過後に処方されます。リハビリテーション初期(6ヶ月から2年)には、頭部へのあらゆる介入、ハイドロマッサージ、泥療法、筋肉の皮膚電気刺激、末梢神経への投射を除き、様々な種類の理学療法が用いられます。寛解が2年以上続く場合、特発性てんかんの治療後のリハビリテーションには、あらゆる種類の理学療法が含まれます。例えば、脳波でてんかん様活動の兆候が見られる場合など、理学療法の実施可能性は個別に判断されます。これらの処置は、主要な病理学的症状を考慮して処方されます。
民間療法
てんかんは非常に深刻な病気であり、発作を抑制する薬が登場している今日において、民間療法で治療するのは少なくとも合理的ではありません。民間療法は使用できますが、医師の許可を得た場合にのみ使用できます。残念ながら、民間療法は厳選された薬剤の代わりになるものではなく、むしろ薬剤の効果を弱める可能性があります。
森に生えた干し草を煎じた湯で入浴するのは、おそらくかなり安全でしょう。昔、てんかん患者はこのように治療されていました。
夏に試せるもう一つの民間療法は、都市部に住む人、例えばダーチャ(別荘)で試せるものです。夏の早朝、朝露が乾く前に外に出て、綿や麻などの天然素材でできた大きめのタオル、シーツ、毛布を芝生の上に広げます。毛布は露に浸しておく必要があります。そして、患者をその布で包み、横たわらせるか座らせます。布が乾くまで外さないでください(この方法は低体温症や風邪のリスクを高めます)。
ミルラ(没薬)の樹脂の香りは、神経系に非常に有益な効果をもたらします。てんかん患者は、1ヶ月間、昼夜を問わずミルラの香りを吸い込むべきだと信じられていました。そのためには、アロマランプにミルラオイル(数滴)を垂らしたり、教会から樹脂片を持ち帰り、その懸濁液を患者の部屋に撒いたりすることができます。ただし、どんな香りでもアレルギー反応を引き起こす可能性があることにご注意ください。
抗てんかん薬を服用している間は、絞りたてのジュースを飲むとビタミンや微量元素の不足を補うことができます。
フレッシュチェリージュースを1日2回、グラス1/3杯ずつ飲むことをお勧めします。この飲み物には抗炎症作用と殺菌作用があり、鎮静作用、血管痙攣の緩和、麻酔作用もあります。また、フリーラジカルを結合させる作用もあります。血液組成を改善し、貧血の発症を防ぎ、毒素を排出します。チェリージュースは最も健康に良い飲み物の一つで、葉酸やニコチン酸などのビタミンB群、ビタミンAとE、アスコルビン酸、鉄、マグネシウム、カリウム、カルシウム、糖類、ペクチン、その他多くの貴重な成分が含まれています。
また、一般的な強壮剤として、緑色のオート麦の芽と、乳白色に熟した小穂からジュースを飲むこともできます。このジュースは他のジュースと同様に、食前にグラス1/3杯を1日に2~3回飲みます。若いオート麦の芽には、ビタミンA、B、C、E、酵素、鉄、マグネシウムなど、非常に貴重な成分が含まれています。このジュースは血液を浄化し、血液組成を回復させ、免疫力を高め、代謝を正常化します。
薬用植物は、煎じ薬、煎じ液、お茶などにして、免疫系、神経系、そして体全体の強化に活用できます。ハーブ療法は抗てんかん薬の代わりにはなりませんが、その効果を補うことができます。シャクヤク、マザーワート、バレリアンなど、鎮静作用のある植物が用いられます。セントジョーンズワートは、伝統医学者によると、発作の頻度を減らし、不安を軽減する効果があると言われています。天然の抗不安薬ですが、バルプロ酸との併用は禁忌です。
マウンテンアルニカの花の煎じ液は、1回大さじ2~3杯を1日3~5回、食前に服用します。乾燥した花を大さじ1杯分、熱湯をグラス1杯注ぎ、1~2時間煎じます。その後、濾します。
当帰の根茎は乾燥させ、粉砕し、1日3~4回、食前に半カップの煎じ液として服用します。1日の服用量は、以下の手順で煎じます。大さじ2杯の当帰に熱湯400mlを注ぎます。2~3時間後、煎じ液を濾し、温めて飲みます。飲むたびに少し温めてください。
ホメオパシー
特発性てんかんのホメオパシー治療は、ホメオパシー医師の監督下で行われるべきです。この病気の治療には、ベラドンナなど多くの治療法があります。
ベラドンナは、無力発作やけいれんの治療に使用され、聴覚症状を伴う部分てんかんにも効果があるとされています。
ヒキガエルは、患者が目覚めているかどうかに関わらず、夜間の発作を止めるのに効果的です。また、コッキュラス・インディクスは、患者が朝起きた時に起こる発作を止めるのに効果的です。
メルクリウスとラウロセラスは、脱力発作や強直間代性けいれんを伴う発作に用いられます。
てんかん症候群の治療には、他にも多くの薬剤が使用されます。ホメオパシー薬を処方する際には、病気の主な症状だけでなく、患者の体質、習慣、性格特性、嗜好も考慮されます。
さらに、ホメオパシーは抗けいれん薬による治療後の迅速かつ効率的な回復に役立ちます。
外科的治療
てんかんの根本的な治療法は外科的介入です。薬物療法に抵抗性で、頻繁かつ重度の局所発作が患者の健康に回復不能な害を及ぼし、社会生活を著しく困難にしている場合に行われます。特発性てんかんでは、保存的治療によく反応するため、外科的治療が行われるのはまれです。
外科手術は非常に効果的です。幼少期に外科的治療を行うことで、認知障害を回避できる場合もあります。
真の薬剤耐性を確立するには、術前検査が非常に重要です。その後、てんかん焦点の位置と外科的介入の範囲を可能な限り正確に決定します。焦点性てんかんの場合、大脳皮質のてんかん原性領域は複数の切開によって除去または切断されます。全般性てんかんの場合、脳半球間におけるてんかん発作を引き起こす病的なインパルスを停止させる外科手術である半球切断術が推奨されます。
鎖骨領域には刺激装置も埋め込まれており、迷走神経に作用して脳の病理学的活動と発作の頻度を減らすのに役立ちます。[ 24 ]
防止
特発性てんかんの発症を予防することはほぼ不可能ですが、てんかんを持つ女性であっても、健康な子どもを出産する確率は97%です。両親の健康的な生活習慣、妊娠の成功、そして自然分娩によって、この確率は高まります。
予測
特発性てんかんの症例の大部分は良性であり、予後は良好です。平均して80%以上の患者で完全な治療寛解が達成されますが、一部の疾患、特に青年期に発症する疾患では、長期にわたる抗てんかん療法が必要となります。場合によっては、生涯にわたることもあります。[ 25 ] しかし、現代の薬剤は一般的に発作を抑制し、患者に通常の生活の質を提供します。


