記事の医療専門家
新しい出版物
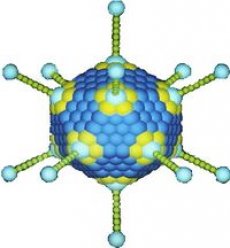
がんの本質を説明するために、変異説とウイルス説という2つの主要な説が提唱されてきました。前者によると、がんは1つの細胞における多数の遺伝子の連続的な変異の結果であり、つまり遺伝子レベルで起こる変化に基づいています。この理論は、1974年にF.バーネットによって最終的な形で定式化されました。がん性腫瘍はモノクローナルであり、1つの体細胞から発生し、その体細胞における変異は、DNAを損傷する化学的、物理的因子、およびウイルスによって引き起こされます。このような変異細胞の集団では、さらなる変異が蓄積され、細胞の無制限の複製能力が高まります。ただし、変異の蓄積には一定の時間が必要であるため、がんは徐々に進行し、発症の可能性は年齢に依存します。
がんのウイルス遺伝学説は、ロシアの科学者LAジルバーによって最も明確に提唱されました。がんは腫瘍形成性ウイルスによって引き起こされ、それらが細胞の染色体と融合してがん性表現型を形成するというものです。しかし、多くの腫瘍形成性ウイルスがRNAゲノムを持つため、それがどのように細胞染色体と融合するのかが不明瞭であったため、ウイルス遺伝学説の完全な認知は一時期阻まれていました。しかし、これらのウイルスにおいて、ビリオンRNAからDNAプロウイルスを複製できる逆転写酵素が発見されたことで、この障壁は解消され、ウイルス遺伝学説は突然変異説と共に広く認知されるようになりました。
がんの性質を理解する上で決定的な貢献を果たしたのは、がん原性ウイルス中の悪性遺伝子であるがん遺伝子と、その前駆物質でヒト、哺乳類、鳥類の細胞中に存在するプロトがん遺伝子の発見でした。
プロトオンコゲンは、正常細胞において重要な機能を果たす遺伝子ファミリーです。細胞の成長と増殖を制御するために不可欠です。プロトオンコゲンの産物は、細胞シグナルタンパク質をリン酸化するための様々なタンパク質キナーゼと転写因子です。後者は、プロトオンコゲンであるc-myc、c-fos、c-jun、c-myh、そして細胞抑制遺伝子の産物であるタンパク質です。
オンコウイルスには 2 つの種類があります。
- がん遺伝子を含むウイルス(1 つ以上のウイルス)。
- がん遺伝子を含まないウイルス(1 種類のウイルス)。
- One+ウイルスはがん遺伝子を失う可能性がありますが、それによって通常の機能が損なわれることはありません。つまり、ウイルス自体はがん遺伝子を必要としません。
One+ ウイルスと One" ウイルスの主な違いは次のとおりです。One+ ウイルスは細胞に侵入しても、細胞を癌に変えることはないか、または非常にまれにしか引き起こしません。One" ウイルスは細胞核に侵入すると、細胞を癌に変えます。
このように、正常細胞が腫瘍細胞に変化するメカニズムは、がん遺伝子が細胞染色体に導入され、細胞に新たな性質を付与することで起こります。この性質により、細胞は体内で制御不能に増殖し、がん細胞のクローンを形成します。正常細胞ががん細胞に変化するメカニズムは、細菌の染色体に融合した溶菌性ファージが細菌に新たな特性を付与する形質導入に似ています。がん原性ウイルスはトランスポゾンのように振る舞うため、このメカニズムはより説得力を持ちます。つまり、ウイルスは染色体に融合し、ある領域から別の領域へ、あるいはある染色体から別の染色体へと移動することができるのです。問題の本質は、プロトオンコ遺伝子がウイルスと相互作用すると、どのようにしてがん遺伝子に変化するのか、ということです。まず、ウイルスは増殖速度が速いため、真核細胞よりもプロモーターがはるかに高い活性で作用するという重要な事実に留意する必要があります。したがって、「1」ウイルスが細胞の染色体上のプロトオンコゲンの一つに隣接する部分に組み込むと、この遺伝子の働きはプロモーターに従属するようになります。ウイルスゲノムは染色体からプロトオンコゲンを奪い取り、後者はウイルスゲノムの構成要素となってオンコゲンへと変化し、ウイルスは「1」から「1+」ウイルスへと変化します。このような「オンコ」ウイルスは、別の細胞の染色体に組み込まれる際に、同時にオンコゲンをその細胞に導入し、あらゆる結果をもたらします。これが、発癌性(「1+」)ウイルスの形成と、正常細胞から腫瘍細胞への形質転換の始まりとなる最も一般的なメカニズムです。プロトオンコゲンからオンコゲンへの形質転換には、他にも様々なメカニズムが考えられます。
- プロトオンコ遺伝子の転座により、プロトオンコ遺伝子が強力なウイルスプロモーターに隣接し、それがプロトオンコ遺伝子を制御することになる。
- プロトオンコゲンの増幅により、そのコピー数が増加し、合成される産物の量も増加する。
- プロトオンコゲンからオンコゲンへの変化は、物理的および化学的変異原によって引き起こされる突然変異の結果として発生します。
したがって、プロトオンコゲンがオンコゲンに変化する主な理由は次のとおりです。
- プロトオンコ遺伝子をウイルスゲノムに組み込み、後者を one+ ウイルスに変換すること。
- ウイルスの統合、または染色体内の遺伝子ブロックの転座の結果として、強力なプロモーターの制御下にあるプロトオンコ遺伝子の侵入。
- 癌原遺伝子における点突然変異。
プロトオンコゲンの増幅。これらの事象の結果は以下のようなものとなる可能性があります。
- 癌遺伝子のタンパク質産物の特異性または活性の変化。特に、ウイルスゲノムに癌原遺伝子が含まれると、癌原遺伝子の変異が伴うことが多いため。
- この製品の細胞特異的かつ時間的な調節の喪失;
- がん遺伝子の合成タンパク質産物の量の増加。
がん遺伝子産物はタンパク質キナーゼや転写因子でもあるため、タンパク質キナーゼの活性と特異性の異常は、正常細胞が腫瘍細胞へと変化する最初の引き金となると考えられています。プロトオンコ遺伝子ファミリーは20~30個の遺伝子で構成されているため、がん遺伝子ファミリーに含まれる変異体は30個程度に過ぎません。
しかし、このような細胞の悪性度は、プロトオンコゲンの変異だけでなく、正常細胞に特徴的な遺伝子全体の働きに対する遺伝環境の影響の変化にも左右されます。これが現代のがん遺伝子理論です。
したがって、正常細胞が悪性細胞へと変化する主な原因は、プロトオンコゲンの変異、あるいは強力なウイルスプロモーターによる制御下に置かれることです。腫瘍形成を誘発する様々な外的要因(化学物質、電離放射線、紫外線、ウイルスなど)は、すべて同じ標的、すなわちプロトオンコゲンに作用します。プロトオンコゲンは、各個体の細胞の染色体中に存在します。これらの要因の影響下で、何らかの遺伝的メカニズムが活性化され、プロトオンコゲンの機能変化が引き起こされ、これが正常細胞の悪性化を引き起こします。
癌細胞は、外来ウイルスタンパク質または自身の改変タンパク質を運びます。これはT細胞傷害性リンパ球によって認識され、免疫系の他のメカニズムの関与によって破壊されます。T細胞傷害性リンパ球に加えて、癌細胞はNK細胞、ピット細胞、Bキラー細胞、そして抗体に依存する細胞傷害活性を持つK細胞といった他のキラー細胞によっても認識・破壊されます。多形核白血球、マクロファージ、単球、血小板、Tリンパ球およびBリンパ球のマーカーを欠くリンパ組織の単核細胞、IgMに対するFc受容体を持つTリンパ球はK細胞として機能します。
インターフェロンや免疫担当細胞によって生成される他の生物活性化合物には、抗腫瘍効果があります。特に、がん細胞は、多数のサイトカイン、とりわけ腫瘍壊死因子やリンホトキシンによって認識され破壊されます。これらは、幅広い生物学的活性を持つ関連タンパク質です。腫瘍壊死因子 (TNF) は、体内の炎症反応と免疫反応の主なメディエーターの 1 つです。免疫系のさまざまな細胞、主にマクロファージ、T リンパ球、肝臓のクッファー細胞によって合成されます。TNF は、1975 年に E. Carswell らによって発見された、分子量 17 kD のポリペプチドです。複雑な多面的効果があり、免疫担当細胞で MHC クラス II 分子の発現を誘導し、インターロイキン IL-1 および IL-6、プロスタグランジン PGE2 (TNF 分泌機構の負の調節因子として機能) の産生を刺激します。 TNFは成熟Tリンパ球などに対して走化性作用を有する。TNFの最も重要な生理作用は、体内の細胞増殖の調節(増殖調節機能および細胞分化誘導機能)である。さらに、悪性細胞の増殖を選択的に抑制し、溶解させる。TNFの増殖調節作用は、逆の方向、すなわち正常細胞の増殖を促進し、悪性細胞の増殖を抑制するために利用される可能性があると考えられている。
リンフォトキシン(TNF-β)は、分子量約80kDaのタンパク質で、Tリンパ球のいくつかのサブポピュレーションによって合成され、外来抗原を運ぶ標的細胞を溶解する能力も有しています。他のペプチド、特にIgG分子の断片であるペプチド、例えばタフテイン(CH2ドメインから単離された細胞親和性ポリペプチド)、Fab、Fc断片などは、NK細胞、K細胞、マクロファージ、好中球の機能を活性化する能力も有しています。抗腫瘍免疫は、すべての免疫系の継続的な相互作用によってのみ確保されます。
ほとんどの人が癌に罹らないのは、変異した癌細胞が発達しないからではなく、発達した癌細胞が悪性腫瘍を増殖させる前に、T細胞傷害性リンパ球やその他の免疫系によって速やかに認識・破壊されるからです。このような人では、抗腫瘍免疫が確実に機能します。一方、癌患者の場合、変異細胞は免疫系によって速やかに認識・破壊されず、自由に、そして制御不能に増殖します。したがって、癌は免疫不全の結果です。より効果的な癌治療方法を確立するためには、免疫系のどの部分が障害を受けているのかを突き止める必要があります。この点で、生物学的および免疫学的反応性調節因子、すなわち免疫担当細胞によって合成され、腫瘍細胞と生体の相互作用反応を変化させ、抗腫瘍免疫を提供する化学物質を複合的かつ一貫して用いる癌バイオセラピーの開発に大きな注目が集まっています。このような免疫反応性修飾因子を用いることで、免疫システム全体だけでなく、活性化因子の形成、増殖、分化、インターロイキン、腫瘍壊死因子、リンホトキシン、インターフェロンなどの合成を制御する個々のメカニズムにも選択的に作用することが可能となり、がんにおける免疫不全状態を解消し、治療効果を高めることができます。リンホカイン活性化キラー(LKI)とインターロイキン-2を用いたヒト骨髄腫の治癒例は既に報告されています。実験的および臨床的ながん免疫療法においては、以下の方向性が示されています。
- 活性化免疫系細胞を腫瘍組織に導入する。
- リンパ系または(および)モノカインの使用。
- 細菌由来の免疫調節剤(最も効果的なのは LPS とペプチドグリカン誘導体)とそれによって誘発される産物(特に TNF)の使用。
- モノクローナル抗体を含む抗腫瘍抗体の使用。
- 異なる方向(たとえば、第 1 方向と第 2 方向)を組み合わせて使用します。
がんの生物学的療法における免疫反応性の調節因子の使用の見通しは非常に広い。



 [
[