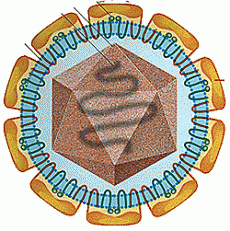
ダニ媒介性脳炎は、ロシア沿海地方から西側の国境にかけての森林地帯、すなわち媒介動物であるマダニの生息地で確認されている感染症です。独立した病理学的単位として、1937年にL・A・ジルベル率いる複合調査隊によるシベリアタイガでの調査の結果、特定されました。調査隊には、著名なウイルス学者(M・P・チュマコフ、V・D・ソロヴィエフ)、臨床医、疫学者が含まれていました。3ヶ月以内に、この疾患のウイルス性が確認され、ウイルスの特性、自然発生地、ダニの活動に関連する季節性など、主要な疫学的パターンが特定されました。同時に、ダニ媒介性脳炎の臨床的特徴と病理形態が記述され、いくつかの予防法と治療法が開発されました。この疾患に関するさらなる研究により、国内だけでなく海外でも蔓延していることが明らかになりました。ダニ媒介性脳炎ウイルスの分離以来、500以上の株が発見されています。マウスに対する病原性の程度、ニワトリ胚線維芽細胞組織培養との関係、その他の指標に基づき、3つのグループに分類されています。第3グループには、弱毒性株が含まれます。
ダニ媒介性脳炎ウイルスには、媒介動物の種類によって、主に東部型(Ixodes persukatus 媒介)と西部型(Ixodes ricinus 媒介)の2種類があります。東部型と西部型のウイルスの代表例におけるゲノムRNAのヌクレオチド配列を調べたところ、86~96%の相同性が確認されました。近年、ギリシャのクリイロコイタマダニから3つ目の型のウイルスが分離されました。臨床経過によって、この疾患には主に2つの亜型があります。東部型はより重症で、西部型はより軽症です。
感染の約80%はダニ刺咬により、20%はヤギ、牛、羊の生乳摂取による経口感染により発生します。実験室感染の事例も報告されています。最も多く感染するのは、就学前および学齢期の児童、そして地質調査作業員です。
潜伏期間は1~30日で、ダニが付着してから7~12日が一般的です。発症は通常急性で、悪寒、激しい頭痛、38~39℃の発熱、吐き気、嘔吐、筋肉痛、筋肉のけいれん、髄膜刺激徴候などが見られます。
ダニ媒介性脳炎には、発熱性、髄膜性、局所性の3つの主要な病型があります。発熱性脳炎は症例の30~50%を占め、髄膜炎の兆候はなく、予後は良好で、無力症はまれにしか見られません。髄膜性脳炎は症例の40~60%を占め、髄液の変化を伴う髄膜症候群を特徴とし、発熱は二波を繰り返すことがあります。
局所型は比較的まれ(8~15%)に観察されますが、特徴的な徴候は髄膜症状と様々な重症度の神経系の局所病変で、麻痺、知覚喪失、その他の神経症状、脳幹の損傷を伴い、呼吸機能障害および心臓機能障害を引き起こします。死亡率は高く、発症後も持続的な合併症が残ります。
臨床検査は主にウイルス学的および血清学的手法によって行われます。ウイルスは血液、脳脊髄液、尿から分離されますが、まれに鼻咽頭スワブ、糞便、そして細胞培養に感染した際の剖検材料からも分離されます。ウイルスは、生物学的中和反応の様々な変異型に分類されます。血清学的手法では、RSK反応、中和反応、RTGA反応、免疫吸着反応において、ウイルスに対する特異抗体が検出されます。
治療は対症療法です。病気の予防には、不活化培養ワクチンという形でダニ媒介性脳炎のワクチン接種が行われます。


