記事の医療専門家
新しい出版物
脳波検査の結果を読み解く
最後に見直したもの: 06.07.2025
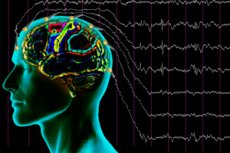
脳波分析は、記録中および記録終了時に実施されます。記録中は、アーティファクト(ネットワーク電流場の誘導、電極運動による機械的アーティファクト、筋電図、心電図など)の存在を評価し、それらを排除するための対策を講じます。脳波の周波数と振幅を評価し、特徴的なグラフィック要素を特定し、それらの空間的および時間的分布を決定します。分析は、結果の生理学的および病態生理学的解釈、ならびに臨床的脳波と相関する診断結論の策定によって完了します。
脳波に関する主要な医療文書は、専門医が「生の」脳波の分析に基づいて作成する臨床脳波報告書です。脳波報告書は一定の規則に従って作成する必要があり、以下の3つの部分から構成されます。
- 主な活動の種類とグラフィック要素の説明。
- 記述とその病態生理学的解釈の要約。
- 前の2つのパートの結果と臨床データの相関関係。EEGにおける基本的な記述用語は「活動」であり、これはあらゆる波のシーケンス(アルファ波活動、鋭波活動など)を定義します。
- 周波数は1秒あたりの振動数として定義され、対応する数値で記され、ヘルツ(Hz)で表されます。この説明は、評価対象となる活動の平均周波数を示します。通常、1秒間の脳波を4~5回測定し、それぞれの波の数を計算します。
- 振幅とは、脳波における電位振動の範囲です。前の波のピークから、逆位相の次の波のピークまでを測定し、マイクロボルト(μV)で表します。振幅の測定には校正信号が使用されます。例えば、50μVの電圧に対応する校正信号が記録時に10mmの高さを持つ場合、ペンの1mmの振れは5μVを意味します。脳波の記述において活動の振幅を特徴付けるために、外れ値を除外し、最も典型的に発生する最大値を採用します。
- 位相はプロセスの現在の状態を決定し、変化のベクトルの方向を示します。一部の脳波現象は、含まれる位相の数によって評価されます。単相性とは、等電位線から一方向に振動し、初期レベルに戻ることです。二相性とは、1つの位相が完了した後、曲線が初期レベルを通過し、反対方向に逸れて等電位線に戻る振動です。多相性とは、3つ以上の位相を含む振動です。より狭義には、「多相性波」という用語は、a波と低速波(通常5つ)の連続を指します。
成人の覚醒時の脳波リズム
脳波における「リズム」という用語は、脳の特定の状態に対応し、特定の脳機構と関連する特定の種類の電気活動を指します。リズムを記述する際には、特定の脳の状態や領域に特有の周波数、振幅、そして脳の機能活動の変化に伴う時間経過に伴う変化の特徴が示されます。
- アルファ(a)リズム:周波数8~13 Hz、振幅最大100μV。健康な成人の85~95%に認められます。後頭部で最も顕著に現れます。aリズムは、目を閉じた穏やかでリラックスした覚醒状態で最大振幅を示します。脳の機能状態に関連する変化に加えて、ほとんどの場合、aリズムの振幅の自発的な変化が観察され、2~8秒間持続する特徴的な「スピンドル」の形成を伴い、交互に増加と減少を繰り返す形で表されます。脳の機能活動レベル(強い注意、恐怖)が上昇すると、aリズムの振幅は減少します。脳波には、神経活動の非同期化を反映した、高周波低振幅の不規則な活動が現れます。短時間の突発的な外部刺激(特に閃光)を受けると、この脱同期は急激に起こります。刺激が感情的な性質でない場合、無リズムはかなり速やかに(0.5~2秒で)回復します。この現象は、「活性化反応」、「定位反応」、「無リズム消失反応」、「脱同期反応」と呼ばれます。
- ベータリズム:周波数14~40 Hz、振幅最大25 μV。ベータリズムは中心回旋部で最もよく記録されますが、後中心回旋部および前頭回旋部にも広がります。通常、非常に弱く発現し、ほとんどの場合、振幅は5~15 μVです。ベータリズムは体性感覚および運動皮質機構と関連しており、運動刺激または触覚刺激に対して消去反応を引き起こします。周波数40~70 Hz、振幅5~7 μVの活動はYリズムと呼ばれることもありますが、臨床的意義はありません。
- ミューリズム:周波数8~13Hz、振幅最大50μV。ミューリズムのパラメータは正常なαリズムと類似していますが、生理学的特性と局所的構造がαリズムとは異なります。視覚的には、ミューリズムはローランド脳領域の被験者の5~15%にのみ観察されます。ミューリズムの振幅は(まれに)運動刺激または体性感覚刺激によって増大します。通常の検査では、ミューリズムは臨床的に意義がありません。
成人の覚醒者にとって病的な活動の種類
- シータ活動: 周波数 4~7 Hz、病的なシータ活動の振幅は 40 μV を超え、ほとんどの場合、正常な脳リズムの振幅を超え、病的な状態では 300 μV 以上に達します。
- デルタ活動: 周波数 0.5~3 Hz、振幅はシータ活動と同じ。
成人の覚醒時および正常時の脳波には、シータ波とデルタ波が少量存在する場合がありますが、その振幅はα波の振幅を超えません。振幅が40μVを超え、記録時間全体の15%以上を占めるシータ波とデルタ波を含む脳波は、病的であるとみなされます。
てんかん様活動は、てんかん患者の脳波で典型的に観察される現象です。これは、多数のニューロン集団における高度に同期した発作性脱分極シフトと、それに伴う活動電位の発生によって引き起こされます。その結果、高振幅の急性電位が生じ、それぞれに対応する名称が付けられています。
- スパイク(英語の spike - ポイント、ピーク)は、持続時間が 70 ミリ秒未満で、振幅が 50 μV 以上(場合によっては数百または数千 μV に達する)の鋭い形状の負の電位です。
- 鋭い波は、時間的に延長される点でスパイクとは異なります。その持続時間は 70 ~ 200 ミリ秒です。
- 鋭波と棘波は徐波と組み合わさり、定型的な複合波を形成することがあります。棘徐波は、棘波と徐波の複合波です。棘徐波の複合波の周波数は2.5~6Hz、周期はそれぞれ160~250msです。鋭徐波は、鋭波とそれに続く徐波の複合波で、周期は500~1300msです。
スパイク波や鋭波の重要な特徴は、突然の出現と消失、そして背景活動との明確な区別であり、背景活動よりも振幅が大きいことです。背景活動と明確に区別できないパラメータを持つ鋭い現象は、鋭波やスパイクとはみなされません。
記述された現象の組み合わせは、いくつかの追加用語によって指定されます。
- バーストとは、周波数、形状、振幅が背景活動とは明らかに異なる、突然の開始と停止を伴う波のグループを表すために使用される用語です。
- 放電はてんかん様活動の突発です。
- てんかん発作パターンとは、典型的には臨床てんかん発作と一致するてんかん様活動の放電です。患者の意識状態を臨床的に明確に評価できない場合でも、このような現象が検出される場合は、「てんかん発作パターン」と特徴付けられます。
- ヒプサリズム(ギリシャ語で「高振幅のリズム」)は、持続性があり全般的に高振幅(>150μV)の緩徐な過同期性活動であり、鋭波、棘波、棘徐波複合、多棘徐波、同期性および非同期性を伴う。ウェスト症候群およびレノックス・ガストー症候群の重要な診断所見である。
- 周期性複合は、特定の患者において一定の形態を特徴とする高振幅の活動バーストです。それらを認識するための最も重要な基準は、複合間のほぼ一定の間隔、機能的脳活動のレベルが一定であるという条件で、記録全体を通して継続的に存在する、個人内の形態の安定性(定型性)です。ほとんどの場合、それらは、高振幅の遅い波、鋭い波のグループと、高振幅で鋭くなったデルタまたはシータ振動の組み合わせによって表され、時には鋭い遅い波のてんかん様複合に似ています。複合間の間隔は、0.5〜2秒から数十秒の範囲です。全般性両側同期周期性複合は、常に深刻な意識障害を伴い、重度の脳損傷を示しています。薬理学的または毒性因子(アルコール離脱、向精神薬および催眠鎮静薬の過剰摂取または突然の離脱、肝障害、一酸化炭素中毒)が原因でない場合は、原則として、重度の代謝性脳症、低酸素性脳症、プリオン性脳症、またはウイルス性脳症の結果です。中毒または代謝性疾患が除外され、高い信頼性で周期性複合症状が認められる場合、全脳炎またはプリオン病の診断が示唆されます。
覚醒している成人の正常な脳波の変異
脳波は脳全体でほぼ均一かつ対称的です。皮質の機能的および形態学的多様性が、脳の様々な領域の電気活動の特徴を決定づけます。脳の個々の領域における脳波の種類の空間的変化は徐々に起こります。
健康な成人の大多数(85~90%)では、安静時に目を閉じた状態で、脳波は後頭部に最大振幅を伴う優勢な a リズムを記録します。
健常者の10~15%では、脳波の振幅が25μVを超えず、すべての誘導において高周波で低振幅の活動が記録されます。このような脳波は低振幅脳波と呼ばれます。低振幅脳波は、脳における同期解除の影響の蔓延を示しており、正常な変異です。
健康な被験者の中には、α波の代わりに、後頭部で14~18Hz、振幅約50μVの活動が記録されることがあります。この活動は、正常なα波と同様に、前方に向かって振幅が減少します。この活動は「速いα波」と呼ばれます。
非常に稀(症例の0.2%)ですが、閉眼脳波検査で後頭部に、周波数2.5~6Hz、振幅50~80μVの規則的で正弦波に近い緩徐波が記録されることがあります。このリズムは、アルファ波の他のすべての局所的および生理学的特徴を備えており、「緩徐アルファ波」と呼ばれます。器質的病理との関連がないため、正常と病態の境界域と考えられており、間脳の非特異的な機能障害を示唆している可能性があります。
睡眠覚醒サイクル中の脳波の変化
- 能動的覚醒状態(精神的ストレス、視覚追跡、学習、および精神活動の増加を必要とするその他の状況)は、ニューロン活動の非同期化によって特徴付けられ、低振幅の高周波活動が EEG 上で優勢になります。
- リラックス覚醒とは、被験者が快適な椅子やベッドに座り、筋肉をリラックスさせ、目を閉じ、特別な身体的または精神的活動を行っていない状態です。ほとんどの健康な成人では、この状態では脳波に規則的なアルファ波が記録されます。
- 睡眠の第一段階は、眠気と同等の状態です。脳波では、アルファ波が消失し、単一または複数の低振幅のデルタ波およびシータ波、ならびに低振幅の高周波活動が出現します。外部刺激はアルファ波のバーストを引き起こします。この段階は1~7分間続きます。この段階の終わりには、振幅75μV未満の緩やかな振動が現れます。同時に、「頭頂部鋭波」と呼ばれる単相性の単相表面陰性鋭波が単一または複数の形で出現することがあり、その最大値は頭頂部で、通常200μVを超えません。これは正常な生理現象と考えられています。また、第一段階は緩やかな眼球運動も特徴としています。
- 睡眠の第2段階は、睡眠紡錘波とK複合体の出現によって特徴付けられます。睡眠紡錘波は、11~15 Hzの周波数を持つ活動のバーストであり、主に中枢誘導で発生します。紡錘波の持続時間は0.5~3秒、振幅は約50μVです。これらは正中皮質下機構に関連しています。K複合体は活動のバーストであり、通常は最初の負の位相を持つ二相性の高振幅波で構成され、紡錘波を伴うこともあります。その振幅は頭頂部で最大になり、持続時間は0.5秒以上です。K複合体は自発的に発生するか、感覚刺激に反応して発生します。この段階では、多相性の高振幅の徐波のバーストも断続的に観察されます。緩徐な眼球運動は見られません。
- ステージ3睡眠:紡錘波は徐々に消失し、振幅75μVを超えるデルタ波とシータ波が分析期間の20~50%の量で出現します。この段階では、K波とデルタ波の区別が困難な場合が多く、睡眠紡錘波が完全に消失することもあります。
- ステージ IV 睡眠は、周波数が 2 Hz 未満で電圧が 75 μV を超える波によって特徴付けられ、分析エポックの時間の 50% 以上を占めます。
- 睡眠中、人は時折、脳波の非同期期間、いわゆる急速眼球運動睡眠を経験します。この期間中、高周波を主体とする多形性活動が記録されます。脳波上のこれらの期間は、夢を見ている状態、筋緊張の低下、眼球の急速運動、そして時には四肢の急速運動の出現に対応します。この睡眠段階の発生は、橋レベルの調節機構の働きと関連しており、その破綻は脳のこれらの部位の機能不全を示しており、診断上非常に重要です。
 [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]
[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]
加齢に伴う脳波の変化
妊娠 24 〜 27 週までの未熟児の脳波は、低振幅 (最大 20 〜 25 μV) の活動を背景に、2 〜 20 秒間持続する、断続的に鋭い波と組み合わされた、ゆっくりとしたデルタ波とシータ波の活動のバーストとして表されます。
妊娠 28 〜 32 週の小児では、最大 100 〜 150 μV の振幅を伴うデルタおよびシータ活動がより規則的になりますが、平坦化期間を挟んだ高振幅のシータ活動のバーストも含まれる場合があります。
妊娠32週を超えると、脳波で機能状態が追跡され始めます。静かな睡眠中は、断続的に高振幅(最大200μV以上)のデルタ波活動が観察され、シータ波と鋭波が組み合わさり、比較的低振幅の活動期間と交互に現れます。
満期新生児の場合、EEG では、目を開けた覚醒状態 (周波数 4~5 Hz、振幅 50 μV の不規則な活動)、活動的な睡眠 (4~7 Hz の一定の低振幅活動に、より高速な低振幅の振動が重なり合った状態)、および低振幅期間が点在するより高速な高振幅波のスピンドルと組み合わされた高振幅デルタ活動のバーストを特徴とする静かな睡眠が明確に区別されます。
健康な未熟児および満期産児では、生後1ヶ月間の安静睡眠中に交代性活動が観察されます。新生児の脳波には、多焦点性、散発性、不規則性の特徴を持つ生理的急性電位が含まれます。その振幅は通常100~110μVを超えず、発生頻度は平均1時間あたり5回で、その主な発生回数は安静睡眠時に限られます。前頭葉誘導において比較的規則的に発生し、振幅が150μVを超えない急性電位も正常とみなされます。成熟新生児の正常な脳波は、外部刺激に対する脳波の平坦化という形での反応を示すことを特徴とします。
成人した子供の生後 1 か月の間に、静かな睡眠の交代性脳波は消え、2 か月目に睡眠紡錘波が現れ、後頭誘導に組織化された優位な活動が見られ、生後 3 か月で周波数が 4 ~ 7 Hz に達します。
生後4~6ヶ月の間に、EEGのシータ波の数は徐々に増加し、デルタ波は減少するため、6ヶ月の終わりまでにEEGは5~7Hzの周波数のリズムが優勢になります。生後7ヶ月から12ヶ月にかけて、シータ波とデルタ波の数が徐々に減少し、アルファリズムが形成されます。12ヶ月までに、遅いアルファリズム(7~8.5Hz)として特徴付けられる振動が優勢になります。1歳から7~8歳までは、遅いリズムがより速い振動(アルファおよびベータ範囲)によって徐々に置き換えられるプロセスが継続します。8歳を過ぎると、アルファリズムがEEGで優勢になります。EEGの最終的な形成は16~18歳までに発生します。
小児における優位リズム周波数の限界値
年齢、年 |
周波数、Hz |
1 |
>5 |
3 |
>6 |
5 |
>7 |
8 |
>8 |
健康な子供の脳波には、過度の拡散性低速波、律動性低速振動のバースト、てんかん様活動放電が含まれる場合があり、そのため、年齢基準の従来の評価の観点からは、21歳未満の明らかに健康な個人であっても、脳波の70~80%のみが「正常」と分類できます。
3~4歳から12歳にかけて、過剰な低波を伴う脳波の割合が増加し(3~16%)、その後、この指標は急速に減少します。
9~11歳では、高振幅徐波という形で現れる過換気反応が、低年齢群よりも顕著です。しかし、これは低年齢群では検査の精度が低いことが原因である可能性があります。
年齢に応じた健康な集団におけるいくつかの脳波変異の表現
活動の種類 |
1~15歳 |
16~21歳 |
記録時間の30%以上にわたって記録された、振幅が50μVを超える緩やかな拡散活動 |
14% |
5% |
後誘導におけるゆっくりとした律動活動 |
25% |
0.5% |
てんかん様活動、リズミカルな徐波のバースト |
15% |
5% |
「正常な」脳波の変異 |
68% |
77% |
成人の脳波特性は、既に述べたように、約50歳まで比較的安定しています。この時期以降、脳波スペクトルの再構成が観察され、アルファ波の振幅と相対量が減少し、ベータ波とデルタ波の量が増加することが示されます。60~70歳以降は、優位周波数は低下する傾向があります。この年齢になると、視覚的な分析で確認できるシータ波とデルタ波が、ほぼ健康な人にも現れます。


