新しい出版物
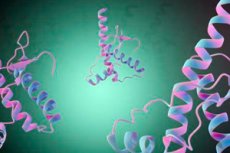
プリオンは、伝染性があり、特定の正常な細胞タンパク質のミスフォールドを引き起こす異常な病原体です。プリオン病は、ヒトだけでなく野生動物や家畜にも影響を及ぼす、治癒不能で致死的な神経変性疾患群の総称です。これらの疾患には、ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)、牛の牛海綿状脳症(BSE、いわゆる「狂牛病」)、そしてシカ、ヘラジカ、ヘラジカに発症する慢性消耗病(CWD)が含まれます。
これらの疾患における鍵となる事象は、プリオンタンパク質(PrPC)が正常な形態から病的な構造(PrPSc)へと変換されることです。病的な構造はニューロンに毒性を示し、変換されていないPrPC分子に結合して自己複製することができます。この自己複製能力により、これらのミスフォールドタンパク質は感染性を持ち、公衆衛生に甚大な影響を及ぼします。
新たな研究で、ボストン大学チョバニアン・アヴディシアン医学部の研究者らは、感染細胞内のPrPSc濃度を低下させることができる10種の化合物を特定し、最も強力な分子は培養されたニューロンにPrPScを適用した場合に見られる毒性を防ぐこともできることを示した。
「嬉しいことに、これらの分子のうち5つはすでに医療現場で使用されています。リムカゾールとハロペリドールは神経精神疾患の治療に、(+)-ペンタゾシンは神経障害性疼痛の治療に、SA 4503とANAVEX2-73はそれぞれ虚血性脳卒中とアルツハイマー病の治療薬として臨床試験中です」と、同校の生化学および細胞生物学教授で筆頭著者のロバート・S・S・マーサー博士は説明した。
研究者らは当初、これらの分子がプリオン増殖に関与すると考えられているシグマ受容体(σ1Rおよびσ2R)に結合することが知られていたため、その抗プリオン特性を研究した。遺伝子ノックアウト技術(CRISPR)を用いて、これらの薬剤の抗プリオン特性はシグマ受容体を標的としていないことを明らかにした。
実験的プリオン感染モデル由来のNeuro2a(N2a)細胞を用い、各薬剤の濃度を段階的に増加させ、PrPScレベルを測定した。次に、CRISPR技術を用いてσ1R遺伝子とσ2R遺伝子を「編集」し、これらの遺伝子がタンパク質をコードしないようにした。その結果、薬剤投与時に観察されるPrPScレベルの低下には影響がないことがわかった。このことから、σ1Rとσ2Rはこれらの薬剤の抗プリオン効果に関与していないという結論に至った。次に、これらの薬剤がPrPCからPrPScへの変換を阻害する能力を試験したところ、細胞外でのこれらの反応には影響がないことがわかった。これは、薬剤の作用には別のタンパク質が関与していることを示唆している。
プリオン病は、血液供給の安全性から脳神経外科で使用される手術器具の適切な消毒に至るまで、公衆衛生に甚大な影響を及ぼすと研究者らは述べています。「臨床的な観点から、この研究は、既にヒトへの使用が安全であることが示されている薬剤に抗プリオン特性があることを明らかにしたと考えています。そのため、特にこれらの疾患に対する効果的な治療法が不足していることを考えると、これらの化合物はプリオン病の治療に再利用できる可能性があります」と、同大学生化学・細胞生物学科教授兼学科長であるデビッド・A・ハリス医学博士は述べています。
これらの結果はACS Chemical Neuroscience誌にオンラインで公開されています。

