新しい出版物
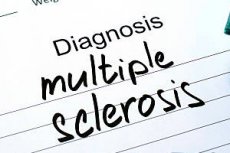
再発とは無関係な障害の進行(PIRA)は、「サイレント進行」とも呼ばれ、多発性硬化症(MS)の現代の見解における重要な統合概念となっています。
「早期の再発寛解型多発性硬化症(RRMS)では、再発を経ずに病状が進行する可能性があるという観察結果は、現在、複数のコホート研究で確認されており、再発患者における病状進行の最も一般的な原因として認識されています」と、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)のブルース・クリー医学博士(MD、PhD、MAS)は述べています。「この観察結果は、MSに関する私たちの理解に根本的な変化をもたらすものです。」
静かな進歩
2019年、Cree氏らは、UCSF EPIC前向きコホートのデータに基づき、MSにおける炎症活動とは無関係な障害の蓄積を説明するために「サイレント進行」という用語を提案した。
研究チームは再発性MS患者を長期追跡調査し、再発は1年間にわたる一時的な障害の増加(P=0.012)と関連しているが、障害の進行は確定していない(P=0.551)ことを発見した。
さらに、障害が進行した患者では、安定した状態を保った患者と比較して、相対的な脳容積がより急速に減少しました。
研究者らは、MS治療が臨床発作に対して高い有効性を示したことで、局所病変の要素が抑制された状態での長期転帰の評価が可能になったと指摘した。これは根本的な考え方の転換への扉を開いた。
「これまで、病気の初期段階での障害の悪化は再発によるものと考えられており、後になって障害が著しく蓄積した後に初めてそれが隠れると考えられるようになった」とクリー氏は指摘した。
「この二段階モデルは誤りだ」と彼は強調した。「二次進行性多発性硬化症と呼ばれるものは、再発活動が極めて有効な抗炎症薬によって抑制されたときに起こるプロセスとほぼ同一である可能性が高い」
「言い換えれば、二次進行性MSは二次的なものではなく、再発と並行して障害の進行性の悪化が起こり、病気の早期に検出できるのです」とクリー氏は述べた。
PIRAの定義
2023年、スイスのバーゼル大学のルートヴィヒ・カッポス医学博士率いる研究者らは、PIRA文献の体系的なレビューに基づいて、一般使用のためのPIRAの統一された定義を提案しました。
「PIRAの最初の記述に続いて、この新しい現象をより深く理解するために、さまざまな患者グループを対象とした多数の研究が行われた」と、同じくバーゼル大学の共著者であるヤニス・ミュラー医学博士は述べた。
「しかし、PIRAには統一された定義がなく、研究の比較や解釈が困難でした」と彼は続けた。「私たちは、この現象に関する最新の知見をまとめ、PIRAを特定するための統一的な診断基準を提案することを目指しました。」
カッポスらは、48件の研究論文をレビューし、その基準を策定した。彼らは、再発寛解型MS患者の約5%に毎年PIRAが発生し、RRMSにおける障害累積の50%以上を占めると推定した。再発関連障害とは対照的に、PIRAの割合は年齢と罹病期間とともに増加した。
このレビューは、クリーらによる以前の研究結果を裏付けた。「PIRAは、MSの初期段階から障害が増加する原因の大部分を占めている」とミュラー氏は述べた。
「これは、MSを再発寛解型と進行型に分類する従来の考え方に疑問を投げかけ、両方のメカニズムが全ての患者と全ての病期に存在し、炎症と神経変性の側面が重なり合っているという見解を支持するものです」と彼は続けた。この現象を認識することで、標的を絞った個別化治療の開発につながる可能性があると付け加えた。
PIRAの診断に関する推奨事項
Kappos らは、上肢機能 (例: 9 ホール テスト)、歩行速度 (25 フィート テスト)、認知テスト (記号数字テストによって測定される情報処理速度) を含む複合測定を使用することを推奨しました。
その他の推奨事項には、12 か月以内の間隔でスケジュールされた標準化された臨床評価を含むデータセットの使用、および画像が 90 日以内に取得された場合にのみ、新しいまたは拡大する T2 病変またはガドリニウム増強病変を臨床イベントに時間的に関連する急性活動の兆候として解釈することが含まれていました。
再発寛解型および進行型MSの両方におけるPIRAを定義または診断するための基準には、臨床イベントで更新されるベースライン参照値、研究者が確認した再発とは異なる場合にのみPIRAによる悪化として分類すること、最初の悪化から6〜12か月後に障害の明らかな悪化を確認すること、および12〜24か月間持続するPIRAの要件を含める必要があるとKappos氏と同僚は付け加えた。
結論
「サイレントプログレッション(無症状進行)」という用語が導入されて以来、PIRAは様々な観点から研究されてきました。ある研究では、最初の脱髄イベントの直後にPIRAを発症したMS患者は、長期的な障害の転帰が不良になる可能性が高いことが明らかになりました。別の研究では、小児期発症のMS患者は比較的若年でPIRAを発症したことが報告されています。また、血清グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)は、脊髄萎縮と同様に、PIRAの予後バイオマーカーとなる可能性も示唆されています。
PIRA を理解することは重要な意味を持つとクリー氏は指摘した。
「再発性MSにおけるPIRAの発症を効果的に予防できる薬剤があれば、その使用は二次性進行性MSと呼ばれるタイプの発症も予防できる可能性が高い」と同氏は述べた。「PIRAを主要評価項目とする臨床試験はまだ成功していないが、治療効果を評価する新たなフロンティアとなるだろう。」

