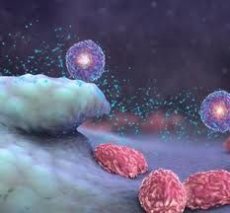
免疫システムには、自身の細胞、組織、臓器を攻撃しないように警告する細胞の種類があることを、UCSFの研究者らが発見した。
UCSFの科学者らは、この発見は、免疫系が体内の細胞を攻撃し破壊するさまざまな自己免疫疾患の治療や、移植拒絶反応の予防のための新たな戦略につながる可能性があると述べている。
UCSFの科学者らが特定した細胞は血液中を循環しており、ワクチン接種後または同じ病原体への繰り返しの曝露後に病原体から身を守るメモリー細胞のコピーである。
免疫システムにおける活性化T細胞と呼ばれる記憶細胞の役割を明らかにするために、UCSFの免疫学者で病理学部長のアブル・アバス氏は自己免疫疾患を持つマウスを使用しました。
彼は、時間の経過とともに、体内の組織(この研究では皮膚)が、制御性T細胞の小さなサブセットを活性化することで自己免疫攻撃から自らを守ることを発見した。
自己免疫疾患は軽度から重度まで様々で、約5,000万人のアメリカ人に影響を与えています。免疫学者は数十年にわたり、これらの疾患はリンパ球と呼ばれる免疫細胞(病原体に対する抗体を産生する細胞を含む)の機能に欠陥があることで発症すると考えてきました。
自己免疫疾患では、リンパ球が自身のタンパク質を攻撃することがあります。例えば、多発性硬化症では、リンパ球は神経を包むミエリン鞘内のタンパク質を攻撃する抗体を産生します。また、全身性エリテマトーデスでは、リンパ球は自身のDNAを産生します。
しかし、多くの場合、自己免疫疾患は制御性T細胞による異常な反応に関連している可能性があると、UCSFの研究者らは述べています。近年、免疫学者は制御性T細胞の重要な役割を理解するようになり、感染からの回復期における免疫反応の抑制だけでなく、自己免疫反応の予防にも関与していることが分かってきました。
UCSFの研究者たちは、自己免疫反応が時間の経過とともにどのように自己抑制または弱まるかを研究したいと考えました。医師たちは、多くの自己免疫疾患において、臓器に対する最初の免疫攻撃が、その後の免疫反応の発現よりも激しくなる傾向があることに気づきました。
UCSFの科学者らは、自己免疫反応を引き起こす皮膚内のオボアルブミンと呼ばれるタンパク質の生成をオンまたはオフにできる遺伝子操作されたマウスの系統を作成した。
このタンパク質の存在は、制御性T細胞の活性化も刺激しました。研究者らがマウスで再びオボアルブミンの産生を増加させると、既に活性化されたT細胞の存在により、弱い自己免疫反応が引き起こされました。
現在、制御性T細胞は、移植臓器の拒絶反応を防ぐことを目的とした治療法としてすでに研究されています。
制御性T細胞集団における長寿命メモリー細胞の発見は、免疫学者が「抗原」と呼ぶ特定の分子標的への攻撃を防ぐために特殊なメモリー細胞を使用することに大きな期待が寄せられていることを示している。
活性化T制御性メモリー細胞の役割はこれまで認識されていなかったため、この研究は多発性硬化症および1型糖尿病における特異的免疫療法の臨床試験の開始に大きな推進力を与える可能性があります。


 [
[