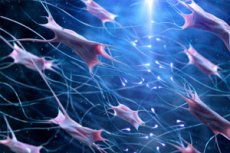
ケンブリッジ大学の科学者らは、神経幹細胞移植によって多発性硬化症の治療をより近づかせた。
ケンブリッジ大学の科学者らが主導した新たな研究は、神経幹細胞移植が中枢神経系のミエリンの修復にどのように役立つかを明らかにしました。この研究結果は、神経幹細胞を用いた治療法が、慢性脱髄疾患、特に進行性多発性硬化症(MS)の治療薬として有望であることを示唆しています。
多発性硬化症(MS)は、免疫系が誤って中枢神経系を攻撃し、神経線維を保護する鞘であるミエリンを破壊する自己免疫疾患です。この損傷は、若年成人における神経障害の主な原因の一つです。
MSの初期段階では、一部の細胞がこのミエリンを部分的に再生することができますが、病気の後期、慢性進行期にはこの再生能力が急激に低下します。この能力の喪失は、進行性MS患者におけるさらなる神経損傷と障害の悪化につながります。
現在の治療法は症状の管理には役立ちますが、損傷や神経変性を阻止したり、回復させたりすることはできません。そのため、MSの進行をより深く理解し、幹細胞技術が治療にどのように役立つかを研究する必要性を強調しています。
革命的な研究成果
ケンブリッジ大学のルカ・ペルッツォッティ=ジャメッティ博士が主導し、ブレイン誌に発表されたこの研究は、進行性多発性硬化症における神経幹細胞移植の可能性について重要な洞察を提供している。
多発性硬化症(MS)のマウスモデルに移植された人工神経幹細胞(iNSC)が、ミエリン形成を担うオリゴデンドロサイトへと成熟することが、初めて研究で示されました。さらに、この研究はヒトiNSC移植の安全性を裏付けるデータも提供しています。
「私たちのデータは、誘導神経幹細胞移植が損傷した中枢神経系内でミエリン産生細胞に効果的に変化できるという重要な証拠を提供し、進行性多発性硬化症の新たな治療法となる可能性を示唆しています」と、
研究の筆頭著者であるルカ・ペルッツォッティ・ジャメッティ博士は述べています。
研究チームはまた、脳萎縮と多発性硬化症の進行を遅らせることを目指し、こうした治療法が神経保護および抗炎症プロセスにどのような影響を与えるかについても研究している。
「幹細胞を用いて新たなミエリンを作製し、病変部位を標的とすることができることを実証しました。これは慢性脱髄疾患に対する標的治療法の開発において重要な前進です」と、
本研究の筆頭著者であるステファノ・プルチーノ教授は付け加えました。
研究の未来とRESTOREプロジェクト
この発見は、今後の研究と臨床試験の発展に重要な意味を持ちます。進行性多発性硬化症に対する革新的な幹細胞治療法の開発に取り組む主要なグループの一つが、ケンブリッジ大学のプルチーノ教授とペルッツォッティ=ジャメッティ博士を含む、欧米の科学者が参加するRESTOREコンソーシアムです。
RESTOREは、国際進行性多発性硬化症連合(IPMS)の支援を受け、進行性多発性硬化症に対する神経幹細胞療法の画期的な臨床試験の実施に取り組んでいます。RESTOREのアプローチは、患者のニーズと意見を最大限考慮するため、患者エンゲージメントを重視しています。
「これらの動物実験の結果は極めて重要です。神経幹細胞が、将来、切実に必要とされているミエリン修復技術の基盤となる可能性を理解する上で、非常に役立ちます。私たちはこの研究を支援できたことを誇りに思うとともに、この研究がすべてのMS患者の病状進行を阻止することに一歩近づくことを願っています」と、
MS協会の科学コミュニケーションマネージャーであるキャサリン・ゴッドボールド博士は述べています。

