新しい出版物
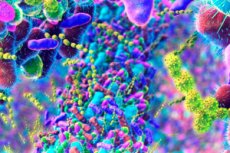
自己免疫性1型糖尿病(T1D)は、インスリンと血糖値だけが原因ではない。腸内細菌叢と自己免疫疾患のリスク、経過、関連する炎症との関連を示す証拠が増えている。食事は細菌叢を微調整する最も早い方法の1つであるため、治療的断食への関心は当然である。すでに健康な人や多くの自己免疫疾患の微生物と免疫回路の構成が変化している。しかし、T1D患者の細菌叢が断食にどう反応するかは、これまで不明だった。Frontiers in Endocrinology誌に掲載された新しい研究は、このギャップの一部を埋めるもので、医師の管理下での1週間の断食がT1D患者の細菌叢を劇的かつ短期間で再構築し、その変化によって健康な人のプロファイルに近づくこと、そして驚くべきことに、別の自己免疫疾患である多発性硬化症(MS)に見られるものと部分的に重なることが明らかになった。
研究の背景
1型糖尿病(T1DM)は、免疫系が膵臓のβ細胞を破壊する自己免疫疾患であり、世界中で約900万人が罹患していると推定されています。遺伝に加えて、環境要因もT1DMのリスクと経過に大きく影響し、近年、腸内細菌叢が重要な「容疑者」の一つとなっています。T1DM患者では、腸内細菌叢の構成と機能が健常者とは異なり、発症前から細菌叢の変化が報告されています。多くの場合、腸管透過性の増加や、免疫に影響を与える代謝物(短鎖脂肪酸、ビタミンA誘導体、トリプトファンなど)の変化が記録されています。これらすべては、「腸内生態学」が免疫応答と自己免疫の経過に影響を与えるという考え方に合致しています。
食事は腸内細菌叢に影響を与える最も迅速な手段であるため、治療的断食や「ポストミメティック」アプローチへの関心が高まっています。モデルおよび健康なボランティアにおいて、長期間の断食は腸内細菌叢の構成を再構築し、動物実験では「断食模倣食」の反復サイクルにより自己攻撃性T細胞プールが減少し、制御性T細胞が活性化することが示されました。同様のシグナルは多発性硬化症モデルでも得られました。しかし、1型糖尿病患者の腸内細菌叢は断食にどのように反応するのか、そして他のグループで以前に報告された断食の「微生物シグネチャー」が再現されるのかどうかという疑問が残りました。
安全性の側面もあります。歴史的に、1型糖尿病における長期的な食事制限は、低血糖/高血糖やケトアシドーシスのリスクがあるため、危険視されてきました。しかしながら、管理された安全性データは蓄積されつつあります。ラマダン断食は、特定の患者において安全に完了しており、医師の監督下での7日間の断食において、糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)を含む重篤な有害事象は報告されていません。これは、「糖尿病を飢餓状態にする」ことではなく、メカニズムと潜在的な補助効果を理解するための、短期間で管理された介入を研究することを目的とした、慎重な臨床プロトコルへの道を開いています。
このような背景を踏まえ、 Frontiers in Endocrinologyのパイロット研究は明確な仮説を立てています。「栄養基質の欠乏」が疾患とは無関係に微生物叢の再編成を促進する強力な要因であるならば、1週間の断食は、健常者や他の自己免疫疾患に見られるものと同様の変化を1型糖尿病患者にも引き起こすはずです。次のステップは、これらの変化がどれほど再現性があり、どれほど長く続くか、そして少なくとも臨床パラメータ(脂質、血圧)の変化と関連しているかどうかを検証し、より大規模で長期の試験に進むかどうかを判断することです。
研究の構成(誰が、何を、いつ)
パイロット研究には、1型糖尿病の成人19名(女性95%)と健康な対照群10名が参加した。全員が入院施設(病院ではないが観察下)で7日間の治療的断食を受けた。野菜ブロス、ジュース、オートブロスによる約200 kcal/日の摂取、水とハーブティーは制限なし。便は0日目(前)、7日目(直後)、150日目(約5~6か月後)に採取され、微生物叢の構成は16Sシーケンスで評価された。著者らはこれとは別に、MSに関するNAMS研究からサブサンプルを追加した。MS患者10名が6か月間隔で2週間の断食を受け(その間、1日14時間の間隔)、断食期間中の食事は最大約400 kcal/日であった。
微生物叢に何が変化したか - 主なもの
最も注目すべき発見は、1型糖尿病患者において、飢餓後に腸内細菌叢が「急上昇」したことです。ベータ多様性によると、7日目には既に腸内細菌叢の構成は健常者のプロファイルに収束していましたが、対照群では同週の全体的なパターンは統計的にほとんど変化しませんでした(おそらく対象者が少なかったため)。150日目には、この影響は弱まり、安定した「新たな均衡」は形成されませんでした。
属別に見ると、21の分類群において、断食後の1型糖尿病患者に異なる変化が見られました。対照群では有意差は低かったものの、変化の方向は同じでした。例えば、
- 減少:Agathobacter、Fusicatenibacter、Oscillospiraceae UCG-003;
- 増殖するもの: Escherichia/Shigella、Ruminococcus トルクスグループ、Ruminococcaceae UBA1819。
より微妙なレベル(ASV、「ほぼ種特異的」)では、DM1ではBacteroides vulgatusとPrevotella属菌の一種のみが増殖し、対照群ではRoseburia intestinalisと他の多くのASVが減少しました。全体として、断食は微生物叢に短時間ながらも強力な「クリック」を与え、その詳細は初期の状態に依存することが確認されました。
「空腹サイン」:1型糖尿病、多発性硬化症、そして健康な個人における繰り返し起こる変化
MS群との比較により、疾患とは無関係にマイクロバイオームの「飢餓シグネチャー」が明らかになった。7つの属がすべて同じ方向に変化し、アガトバクター、ビフィドバクテリウム、フシカテニバクター、ラクノスピラ科UCG-001が減少し、エリシペラトクロストリジウム、大腸菌/赤痢菌、アイゼンベルギエラが増加した。これは、非自己免疫集団を対象としたより大規模な研究でも示されている。第2段階では、MSは高い再現性を示した。有意なASVの約半数が、飢餓の2週間で繰り返された。この図は、一般的な飢餓の生物学的特徴と一致している。「植物繊維を好む」(ラクノスピラ科の多く)が減少し、ムチンおよびグリコサミノグリカンを破壊する(R. gnavus、R.torques、Hungatella)が増加し、宿主の資源に切り替えている。アイゼンベルギエラはケトーシスと関連があり、β-ヒドロキシ酪酸を燃料として利用する可能性があります。
これは健康指標に関係しますか?
著者らは、「細菌」の変化と1型糖尿病患者および対照群の臨床マーカーの変化を比較した。多重比較を調整した結果、9つの有意な関連性が得られた。例えば、Oscillospiraceae UCG-002はLDLの動態と相関し、対照群ではHDLおよび拡張期血圧にも相関していた。対照群のErysipelatoclostridiumとT1DMのRomboutsiaの増殖は血圧の低下と一致していた。LachnospiraはT1DMにおける尿中クエン酸値の減少と相関していた。これらは相関関係であり因果関係ではないが、個々の分類群が脂質および血管緊張に及ぼす影響に関する文献と一致する。
これは空腹の生理学にどのように当てはまるのでしょうか?
論理は単純です。食物基質が不足すると、幅広い代謝能力を持ち、宿主の資源(粘液(ムチン)、グリコサミノグリカン、ケトン体)にアクセスできる微生物が勝利します。したがって、断食は生態系を食物繊維の活発な発酵菌(アガトバクターとその近縁菌は酪酸を大量に生産し、食物繊維を「好む」)から「雑食菌」および「粘液を食べる菌」へと自然に変化させます。同様の変化(アッカーマンシアの増殖を含む)は、他のグループにおいて3~10日間の断食後に既に報告されています。今回の研究では、1型糖尿病においてもこの傾向は変わらないことが示されています。
これは1型糖尿病患者にとって何を意味するのでしょうか?
- これはマイクロバイオームに関するものであり、飢餓による「糖尿病治療」ではありません。変化は短期的なものであり、主に細菌の構成に関係しています。5~6ヶ月にわたる安定した長期的な「再構築」は記録されていません。
- 安全性が鍵です。1型糖尿病患者の場合、モニタリング条件下では7日間の断食は可能です(パイロットスタディではDKAは認められませんでした)。また、特定の患者におけるラマダン断食の安全性に関するデータもあります。しかし、これは自宅で実験する理由にはなりません。低血糖/高血糖、そしてケトアシドーシスのリスクは現実に存在します。
- 実用的なメリットはどこにあるのだろうか?研究者たちは2つの方向性を示唆している。(1) 血圧と脂質の改善に関連のある分類群を理解すること。(2) 1週間の断食をせずに、空腹感のサインを「ソフト」な食事療法(食事時間、食事構成)やプロバイオティクス/プレバイオティクスで再現できるかどうかを検証すること。
制限
これは小規模グループを対象としたパイロット試験であり、主要な統計値はDM1によって「引き出され」、対照群では有意性が低下しました。手法は16S(分類学であり、機能ではありません)であり、ウイルス/マイコバイオームのプロファイリングは行われていません。臨床マーカーとの相関は連関性があり、特定の細菌と、例えばLDLとの因果関係はまだ検証されていません。そして最後に、その効果は一時的であることが判明しました。飢餓の「痕跡」は数ヶ月以内に消えてしまうのです。
科学は次に何をすべきでしょうか?
- 臨床目標(血糖変動、血圧、脂質)、マルチオミクス(メタゲノミクス/メタボロミクス)、および効果の持続性のモニタリングを伴う、より大規模な RCT。
- レジメンの比較: 断食週とインターバルウィンドウ (例: 14 ~ 16 時間)、ケトジェニック段階、「後模倣」プロトコル。
- 微生物叢のターゲット: 1 型糖尿病患者において、厳格な断食を行わなくても食事やサプリメントで「空腹サイン」を再現できるかどうかをテストします。
出典:Graef FA他「断食は腸内細菌叢の特徴的な変化を引き起こし、その影響は1型糖尿病患者にも及ぶ」 Frontiers in Endocrinology、2025年8月13日。DOI 10.3389/fendo.2025.1623800

